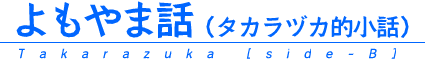
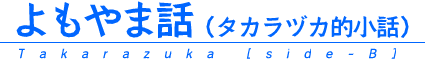
私には、殺しの場面にひとつの理想というのがあって、それは、刃物を用いて決してピストルで殺さない、ということである。その場合にも、限りなく「きれい」でなくてはならない。あくまでその「きれい」の基準は私であるが、怨みつらみが隠っているとか、これでもか、という感じではなく、あくまで無機質的・機械的なのがよい。できることなら、そこには感情など存在しないほうがよい。当然、台詞や音楽や効果音や、そのほかの効果もないほうがよい。これで完璧である。あとは、役者次第。
果たして、「清く、正しく、美し」い宝塚で、このような殺人の場面が上演できる日は来るのであろうか。
役者の希望としては、独断と偏見で、真琴つばさ・姿月あさと・星奈優里・千ほさちを挙げておく。さぞかし美しい殺人者となるだろう。(1996.11)
殺し場に理想があるように、殺し役にも、理想がある。それは、色気が感じられることである。無表情で冷たい顔から、背筋に震えがくるような、なんともいえない感情を私が感じれば、それでいい。どれもこれも、私の嗜好の問題であるのだが。
そんな役をできる人を独断と偏見で選んだら、真琴つばさ・姿月あさと・星奈優里・千ほさちになった。特別な理由ははい。なんとなく、似合うんぢゃないのかなと思ったまでのことである。
理由はあとからついてくるものなので、真琴つばさがなんで殺し役が似合いそうなのかを考えてみる。
「ミリオン・ドリームス」ミリオン・ビーツのレッド・ベレーが、そう思うきっかけとしては大きい。月組版のもそうだけど、ロンドン版で、スモークに霞んでみえる真琴サンが、かっこよかったんだな。あれは、現代版フレーメンの笛吹きみたいだったけど、笛吹きに相当するレッドベレーは、得体の知れない存在だった。またこれが似合ってる。
同じくダーク・ドリームのダークドールも要因にある。天海祐希とキスする(という設定の)真琴つばさはは、なかなか怪しかった。あの場面は珍しくアブノーマルな雰囲気を漂わせていたけど、やはり、芝居ぢゃ、ああ云うのは無理かも。
黒燕尾を着てシルクハットを被って佇んでいる真琴つばさとは、一種独特な雰囲気を醸し出している。ちょっと紫苑ゆうみたいかもしれない。あまり人間ぽくないし、少なくとも私はそう思う。つまり、真琴つばさの非人間的なところをかっているのだ。
真琴つばさと同じく、レッドベレーを観て、である。もともと、あれは人間でない設定なのかもしれない。というよりその方が考えやすい。テレビで見た限りだから、よく判らないけど。だから、殺し役が似合いそうというのは、あくまでレッドベレーが基準になっている。
ミリオン・ビーツがなかったら、きっと姿月あさとに殺し役をやってもらいたいなんて思わなかったと思う。それくらい、レッドベレーは印象に残った。その後の役で、姿月あさとが魅力的だったといえば、「結末のかなた」の明智小五郎くらいで、ラッセルも悪くはないけど、わたしは、あまり。
ずんこさんはいつも笑っている、というイメージのほうが強いので、あまり殺し役の姿月あさとは考えにくい。だから、たまに、笑ってない、いい人でない役をみたり知ってしまうと、こういうことを考えてしまう。
こちらを参照(現在リンクしてません)
「結末のかなた」の不二子がなかったら、私はこの人を挙げなかっただろう。結構不二子は賛否両論だったような気がするが、私は良かったと思う。
何が良かったって、黄金仮面をつけて脱出するところとか、一番好きなのは、大仏の中でルパンと一緒にいるところ。この二人はもう最後までいってるのね、という感じが好きなわけだ。なんとなく怠惰的というか。
最後まで、不二子は明確に感情を表さない。実力がまだついていってないという意見もあったけど、能面みたいに無表情なのだ。というより、日本青年観B席からオペラグラスなしで舞台を観ると、いかに視力の良い私でも顔まではよく見えない、ということである。でも、グラフとか歌劇の写真を見ても、あまり表情は見えてこない。
これが、よい。少なくとも私の考える殺し役には合う。コノ人ハ一体何ヲ考エテイルノダロウってなことを客席(および、ブラウン管のこちら側)で、想像したい。(1996.11)
再演希望も含めて、今後の宝塚で上演してほしいものを、ずらっと挙げる。
いかがなものだろう。結構イケそうな気もするけれど。個人的には、娘道成寺をバウホールで石田昌也氏か酒井澄夫氏の演出で観てみたい。(1996.12)
一番よく観ていた1994年に次いで、宝塚を観た年となった。といっても、5月「結末のかなた」(月組)7月「CAN-CAN」「マンハッタン不夜城」(月組)11月「アナジ」(雪組)の三作だけだが。
それにしても、今年はオリジナルの芝居がほとんどない。大劇場作品でオリジナルだったのは星組「ふたりだけが悪」くらいで、「ELISABETH」を筆頭に「CAN-CAN」「How to Succeed」と海外ミュージカルの当たり年であった。また月組「チェーザレ・ボルジア」、雪組「虹のナターシャ」は原作ものである。
なんと言っても、今年の話題は「エリザベート」である。おまけに雪組トップ一路真輝、星組トップ娘役白城あやかの退団作品となり、話題沸騰だ。ウィーンで大人気を博しているこの作品を、宝塚がどう料理するかが注目された。特に現地では床がめくれるが、それができない宝塚はどうするか。装置については、鏡を効果的に使って不可思議な雰囲気を醸し出していたと思う(あれだけの鏡があったら、私はきっと発狂してしまうに違いない)。
私が観た中で文句なしに面白かったのは、「結末のかなた」である。「アナジ」はいろいろつっこみながら楽しんだ作品だ。「CAN-CAN」「マンハッタン不夜城」はどういうわけかあまり印象に残っていない。
今年は宝塚に参加した年だった。宝塚のホームページのお便りコーナーに投書した。最近はごたごたしているし、私も忙しいので覗くだけにとどまっている。「宝塚グラフ」の組別ランキングにも雪組の回には葉書を出したし、「歌劇」誌10月号には植田紳爾氏に出した質問はがきが掲載された。自分の名前を確認するまでそんなことすら忘れていたうえに、質問の大半が植田氏に喧嘩を売っているような内容だったにも関わらず、「植田先生にとって宝塚とは?」などと云うどうでも良いものだった(当然か)。
'95年は地震と天海祐希の退団がビッグニュースだったが、'96年は小さいながらいろいろあった年だと思う。'97年は、話題づくりなんてしなくていいから、オリジナル作品をもう少し観たい(と思ったら、月組の「バロンの末裔」があった)。(1996.12)
やっぱり殺される場合は、刃物で頚を掻き斬られるか、胸を一突きだろう。このとき、殺される人は少し宙を仰いでほしい。できれば、障子にその影が映った状態での殺し場だと好い。スモークの中にぼんやりでも好い。
殺し役は話に絡んでくることが多いけど、殺され役は必ずしもそういうわけでもない。でも、どちらにしても美しく死んでいってほしい。
「美しく」というのは、ぐちゃぐちゃに殺されるのが嫌いだからである。そういう死体を見るのも好きではない。でも、どういう風に美しいのかというと、実は困ってしまう。とりあえず、未練がましくしつこく生きていないことである。遺言もこの世への未練も云いっこなしである。それと、その殺し場全体が視覚的に美しいこと。桜の花びらとか、金粉とかが舞っちゃったりして。スモークほど大袈裟でなくてもいいのだけど、お香を焚いて(某劇団の影響か)。あと、殺され役は、あまり苦痛に顔を歪めない。
そういう中で殺される役だったら、男役より、少年とか娘役の人がいいかな。ルドルフ少年みたいな感じの少年とか、遊女とか、ものすごく純粋な人とか。あとは、執り憑かれちゃった人も。誰が似合いそうと云うのではない。存在が危ういこと。エキセントリックな演技がみたい。(1996.12)
昨年に引き続いての、元旦生中継。今回は月組「バロンの末裔」である。残念なことに、久世星佳のサヨナラ公演となってしまう作品である。
正塚晴彦演出作品は、月組「銀の狼」(これはテレビで)花組「ブラック・ジャック」しか今まで観たことがないことに気付き、「なんかいつもと違うかも〜」なんてこと云えないのである。なんとなく、「正塚作品はシリアス」というイメージがあったので、思ったより軽くて、ちょっと意外な感じ。
話は、う〜んという感じで、若干物足りない気がした。私は。星組「二人だけが悪」のようにならないようにしたのだろうか。それとも、お正月を挟むことを意識したのかな。そうではなくて、例の「宝塚の器」を意識したのだろうか。
最後話が急展開で、ホテルを経営するに至った過程が暗転で処理されていて(たぶん)、私はどうしてなのかがよくわからなかった。それはそれで旨いのだけど。お金を返しきれたということなのかな。あと、絡んでくる人達も書き込み不足とでもいうのか中途半端な感じがした。 と思うほど観ていないのだけどね。 まあ、テレビなもので、映っている人が限定されて、舞台全体の様子がわからないということもあるのかもしれない。パンフも持っていないし、テレビ観劇感想文だし。
久世星佳のローレンスとエドワード一人二役が、どこで入れ替わっているのかがわからないと云うのが、すごい。今までは一人二役はあっても、二人が同じ場面に居るということは「ブルボンの封印」以外は私は知らない。「ブルボン〜」の時は下級生に仮面を被せて後ろ向きにしていた。
今回の寝室の場面は、ベッド(御簾が降ろされている)に横たわっているローレンスと会話するエドワード。吹き替えを使っているのは明らかなんだけど、エドワードとして登場していた久世星佳が、あれれ、ローレンスになっている。怪しいのは水を渡すとこだけど、どうやって替わったんだろう。よく観ていたのにわからなかった。(1997.1)
「宝塚アカデミア 1」という本が、青弓社と云うところから出版されている。その中の「特集植田紳爾の世界」で、川崎賢子さんが「大劇場文法は、近場の客に対するアピールと遠目の客に対するそれとの二本立て」というようなことを書いていて、その一部分の、要約すると「植田紳爾は、近場の客に対するアピールを量的に延長拡大することで遠目の客にもアピールしている」というような文を読んだときに、私は、ヴァルター・ベンヤミンの「複製技術時代における芸術作品」(1936)を思い出してしまった。
それはどういうことかというと、ものすごく簡単にいってしまうと、「複製技術の発展で、オリジナルの持っている価値(「いま」「ここに」という一回性)、つまり、礼拝的価値(アウラ)がなくなって、その結果、芸術が大衆化していく(多くに人に行き渡る)んだよ」ということである。それで、そのことをベンヤミンは肯定しているのだ。
まあ、ベンヤミンのほうは映画の話だし(そのわりにはテレヴィジョンのことを暗示した内容で面白い)、川崎さんの話とは関係ないのだけど、ちょっとそういうことを考えたわけだ。
ところで、話は全然変わる。
まだ行ったことがないけれど(今度行くけど)、1993年に宝塚大劇場が新しくなってきれいになった。東京宝塚大劇場も新しくなる。なんとなく、宝塚が、オペラとかみたいに、「一部の人のための芸術作品」に近くなっているのではないかな。きっと観劇料金も値上げするだろうし。東京公演の1100円はもう無理かもしれないけど、せめて末席2500円くらいをめざしてほしい。もうちょっと気楽に行ける雰囲気を醸し出してくれないかな。まるでフォーマルな服を着ていかないといけないみたいぢゃん。だから宝塚が今後「芸術」としていくのか「大衆娯楽」としていくのかが、気になるところ。往々にして「芸術」は一般大衆にとって取っつきにくい物である。政府によって「芸術」としての保護を受けないように期待したい。
ちなみに末席2500円くらいとしたのは、小劇場で芝居を見る場合、当日券の値段がそれくらいだからだ。できればそれ以内がいい。(1997)
私は、殺し役も好きだけど、悪役も好きだ。殺し役だって悪役かもしれないけど、別にしておく。
私の好きな悪役のタイプは、主役(とか、ヒロイン)を追いつめるものである。悪事を働く悪役もまあ意味的には含まれるけど、敵役に近いかな。例えば、「銀の狼」のジャン・ルイ(久世星佳)。大統領を殺しそっくりさんを替え玉にして裏で操り、殺した大統領の娘で、対立候補に情報を流そうとした妻である麻乃佳世のミレイユを殺そうとまでする人だ。結局最後はシルバ(涼風真世)に殺されるのだけど、その前にミレイユにキスするところが、良いんだな。これが。実はジャン・ルイはミレイユのことを愛していたんだって!その愛は、端から拒絶されている。
まあ、私の好きな悪役のタイプというと、こんな感じである。あと、「アポロンの迷宮」のマルセル・ド・モンテスキュー(紫苑ゆう)とか。綺麗なものだから手元に置いておきたいという感覚は、私と通じるものがないわけではない。なんとなく、マルセルの気持ちは分かった。
私が星奈優里で観たい、裏で何してるのかわからなくてやっぱり悪い人だった、というのもよいな。だからといって、ブラック・ジャックで海峡ひろきや天地ひかりや詩乃優花がやったおかしな人達が嫌なわけではない。あれはあれで、結構好き。ただ、私の嗜好としては、断然追いつめ系がよいのである。
1年に1作はこういう悪役がでてくるものを観たい、と切に願っているわけです。でも勧善懲悪は駄目。(1997)
タカラジェンヌさんって、お酒強そうですね。はっきり云って、タバコを吸っている姿はあまり見たくありませんが、宴会には居合わせてみたいという気もします。ちなみに私自身は飲ま(め)ないので、酔った人を観察しています。
なんでこんな話題なのかというと、夢の中に雪組の花總まりが出てきたからなのです。夢の中で、私はなぜか彼女に京王アートマン府中店を案内されていました。その後伊勢丹府中店2Fに食べに行こうという話になり、そこで夢は終わってしまいました。が、その時に夢の中の花總まりは、なぜか柳葉敏郎が売っていた「白城あやかも酔った」という強いお酒(日本酒)に挑戦すると云ったのです。私は「花總さんはバスで国分寺に出て中央線で帰るのか、京王線で新宿に出るのかどっちだろう」とか思っていました。
なんで白城あやかがでてきたのかはわかりません(「パパラギ」のシャンパン戦争のせい?なぜならその白城あやかは「うたかたの恋」のマリーの白いドレスにワイングラスを持ってにっこり笑っていたのですから)。そんなこんなで、タカラジェンヌはお酒強そう、と思うのです。夢にでてきた花總まりは元星組だし、白城あやかは星組生徒。星組といったら、エマ・エージェンシー。この宴会余興団体が、私の「ジェンヌお酒強い」説に拍車をかけているかもしれません。(1997)
いずれ、宝塚で上演してもらいたいもの。
ホラーである。宝塚でホラー。観たい。ひとつひとつの話はそんなに長くないから、オムニバスで観たい。三本立ての真ん中、というテもある。「浅茅が宿」、「吉備津の釜」、「蛇性の淫」を酒井澄夫氏か、石田昌也氏か、太田哲則氏の演出で。
これも短編集だから、「雨月物語」同様オムニバスか三本立ての真ん中。演出も同じ。岡本綺堂は「半七捕物帳」が有名だけど、怪談といえばこれ。じわじわと怖い。でも宝塚向けではないかも。
結構怖い話が好きである。怖いと云っても、車にひかれそうになって怖かったって云うんぢゃなくて、サスペンスとか怪奇物とか。怪奇物は、最初と最後が一致しない終わりかた、辻褄が合わなくて気持ちの悪い終わりかたでないとだめだなあ。幽霊とか妖怪とか人の心なんて不条理なものだから、すっきりしないほうが断然いいのである。(1997)
手塚治虫の漫画で、宝塚歌劇団そのものが舞台。もちろん「宝塚」とは云っていないが。とても短い話だけど、謎解きをもっと綿密にすれば1時間30分になるはず。歌劇団のスターである某国の王女が暗殺されるところから事件は始まる。演出は正塚晴彦氏か木村信司氏か、でなければ劇中に「宝塚」を入れるのが好きな植田理事長。
謎解きは好きである。「MYST」を今やっているところである。なかなか先に進まないんである。宝塚で謎解きをやるときは、座談会でも舞台写真・劇評・絵と文・楽屋日記・グラフトークスペシャル・その他諸々でも謎を明かさない。観た人も絶対口外しないで。それは犯人探しの場合もしかり。今までは、どこかから漏れてきていた。少なくとも一回目を観るまで、観客は犯人を知らないというのが一番望ましいのである。もちろん、犯人が誰かわかるような配役もなしである。日替わりとかいいかも。
そんなで、今宝塚で観たいものは、「怪奇」と「謎解き」である。(1997)