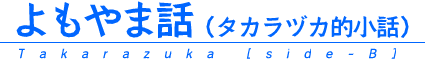
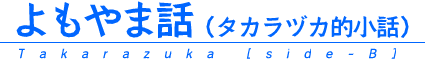
退団とは実に惜しい。テレビ中継も含めて印象に残った白城あやかの役について短く感想を述べていこうと思う。(1997)
愛新覚羅溥傑をしていた紫苑ゆうと並ぶと、よく似ていたのがとても印象的。綺麗だし、大きいし、すごい娘役だとテレビ観劇ながら思った。
これがきっかけで宝塚に本格的(?)にはまる。きつめのお化粧をして踊る姿がかっこいい。さっきのフレイヤ姫の人とは思えない。
聖少女といいつつアイツウが化けたもの。アイツウはサミーさんがしていて、サモア版「恋する悪魔」といった感じ。誘惑役第2弾くらい。結構色っぽかった。
最後に過去への思いを断ちきるように真正面を見つめる姿をみるとかえって泣けてきた。しっとりしていてとても味わい深い。
帝国ホテルでヘルマンに家族について聞かれたときのベロニカの顔の、少し動揺した感じが私は好き。ザビーネに再会すればこの人はきっと救われるんだろうな、とカウフマンにベルトで打たれた後に銀橋で歌う前の独白を聞いていて思った。
誘惑役第4弾。南極版「雪女」。観測隊はしらせに乗っているのか?
本当に綺麗である。一幕の最後で鏡の中からでてきた姿はやっぱり素晴らしい。
最近、というほどでもないのだが、雪組の「マ・ベル・エトワール」というショーのプロローグの音楽が、かっこよかったので嬉しい。なぜって「プログレ」だったからである。まあ、本当にプログレのことが好きでよく知っている人が聴いたらそうでもないんだろうけど。
宝塚でこんなに「プログレ」しているのを聞いたことがない。少なくとも私はない。例えば、座談会かなにかで演出家が「ロック調でいきます」といってロック調に聞こえてきたためしがあまりない。R&Rはロックではないだろう、と言いたくなるものが多いのだ。「調」が付いているとはいえロックと言ったからにはロックでいこうよ。音とかメロディが古い。ひどいのは特にギターで、「エリザベート」を観て初めて、宝塚でもロックの音が出せるんぢゃんと思ったほどである。ただし、フィナーレでこけた。あのフィナーレのギターの音がねえ。
で、「マ・ベル・エトワール」である。プロローグのプログレである。曲自体は6分でさほど長くはないけれど、きちんと主旋律が変わっているのが偉いのだ。「宝塚チック」に聴こえなかったのも偉いのだ。減り張りも利いていたし、本当にやればできるのにどうして普段からやらないんだろう。
ショー音楽で一番好きなのは、「ジャンクション24」で使われた "PICK YOURSELF UP" である。オリジナルではなくてジェローム・カーンの曲であるが、編曲の仕方も上手くて、それに大浦みずきと磯野千尋と詩乃優花のダンスもいいね。
生オーケストラより、録音された音楽を使った場面のほうが好きな場面としては多いのだが、どうしてなんでしょうかねえ。(1997)
私は、宝塚関連の書籍はあまり持っていない。ハードカバーは買う前にどうしてもムムム、と考えてしまうのだ。だから、たいていは本屋で立ち読みか図書館で借りることになるので、出版されてから半年とか一年以上あとにようやっとお目にかかるという次第。最近読んだのは、「FOR BEGINNERS 宝塚」(梅原理子・著 現代書館)、「MARIKO」(麻路さき・著 東宝株式会社)で、どっちも市立図書館の本である。
「FOR BEGINNERS 宝塚」は、以前ちょっと立ち読みしたことがある。コラムの『「南京虐殺」というセリフ』ばかり読んでいたという… どうして「紫禁城の落日」から「南京虐殺」というセリフが消えたかという内容で、1991年11月30日の朝日新聞に載った記事。読んだような覚えあり。そういえば NHK の劇場中継では「南京の嫌な噂」になっていた。そこら辺を今度調べてみようかなー。ビギナー向けに出版された本の中では一番これが好き。勢いで読める上に縦書きでないから、どこから読んでもいいという気楽さがある。絵も多いし。イラストは星組に在籍していた乙原愛さんなのさ。
「MARIKO」・・・表紙がシンプルでいい。宝塚の本は結構ゴテゴテしていて表紙を見て、ウっ、と思ってしまうのが多い中ではかなりポイントが高い。私の中では。もっともエッセイではあまりそんなことはないのだけど。宝塚の人が出したエッセイは、とりあえず読むようにしている。その人の考え方とかものの見方が割とわかりやすいような気がするので。一番興味深かったのが、「4月4日」。この日は大学の入学式、ではなくて、オカマの日なんだそうだ。知らなかった。歌舞伎役者はまあわかるけれど、宝塚の男役は異性装ということなのかしらん。こういうパーティーはおもしろいらしいので、公演中でないなら出てみるといいかも。それにしても、宝塚ではいつも宴会をやっているイメージがあるのだけど(特に星組)、ほんとに宝塚の人はよく食べているなあ、という感じ。一度で良いからその場に居合わせてみたいぞ(特に星組)。 (1997)
谷正純氏についていろいろ。「アナジ」を観てから大分時間も経って、興奮が冷めてきたところ。
谷氏のオリジナルは、どういうわけか人がよく死ぬ。必ず死ぬ。死なないというのは、「白夜伝説」くらい。一度死んだ後にオーディン(紫苑ゆう)によって生き返っている。それに泣かせ系でないのは「ル・ミストラル」である。後は、出雲綾と美々杏里の怪演で評判だった「FILM MAKING」(つまりおもしろかったってこと)と、「秋〜冬への前奏曲」。「秋〜冬〜」に限って云えばよく内容を知らないのだが。まあ、それくらい人が死んで泣かせるのが多いような気がするのである。
「白夜伝説」はもとがものすごく中途半端なのに加えて、いったん死なせて生き返らせたために話がややこしい。「冬って何?どこへいったの?」という具合である。しかもガイ(麻路さき)は心を奪う騎士なんだけど、途中から心を奪う方法が変わってしまったのか、私を混乱に陥らせた。ガイを見ちゃいけないの?心の目で見れば平気って、さっきまでは「心を奪え、ガイ」っていって音楽がなったらオーディン様とミーミルちゃん(花總まり)以外はみんな心を奪われていたぢゃないか。星組の人が「心の綺麗な人にはわかる」みたいなこと言っていたし私は純粋ぢゃないんだな、と妙に納得したのだけど。宝塚を劇場で観るようになって初めての迷作。
その次に観た谷オリジナル作品は、月組「エールの残照」である。私は血迷って東京公演でわざわざ大劇場メンバーのを観てしまった。失敗。で、これも人が死ぬんだ。死体累々ではないけれど、ダニエル(久世星佳)とロージー(麻乃佳世)がね。やっぱり死ぬところでタニは泣かせる。ダニエルが自爆するところと、シャムロック(天海祐希)が死んだロージーをかついで歌うところ。死んだら泣くという谷氏の鉄則みたいなものなのでしょうかねえ。一番よかったところは、シャムロックが「両方(アイルランド義勇軍と大英帝国)から敵と見られている可哀想な平和主義者だ」といっているところ。戦争状態の両者の間で中立を保つのってそういうモノだよ。わかっているだけ偉い。でも君自分の主義主張に酔ってない?
その「エール〜」の次が「アナジ」なのである。「エール〜」は支配する「イギリス」と被支配の「アイルランド」の対立、そこに平和主義者の三つどもえだった。「アナジ」も支配する「徳川」の名を借りた松浦隆信と、そこに対立することになってしまった紅蓮丸乗組員達に、隠れキリシタンと島津に侵略された琉球が加わる。尹玉琴は朝鮮使節団で、幕府と李氏朝鮮の政府間同士の交流なので松浦側につく(が最後に殺される)。早い話「強者」と「弱者」の対立なのだ。
谷氏オリジナルの泣かせのパターンとして結構この対立を描いているものが多いことに気がつく。1992年から見ても、「高照らす日の皇子」(月組/バウ/1992)、「エールの残照」(月組/1994)、「アナジ」(雪組/バウ/1996)と3作ある。共通しているのが強者が悪として描かれるところ。社会的弱者は往々にして存在自体が抹殺されることが多いので悲劇的である。でも、弱者が強者に殺されることによって泣かせる谷氏に、私はいまいちなじめない。「エールの残照」はまた少し違うけれども。人が死ねばいいってもんぢゃないでしょう。それ以外では泣かせられないのか?いくら死ぬときにはその人の生き様が見えるって云ったって、死に過ぎである。しかもパターン化しているから、こっちも「またか」と思ってしまうのであった。(1997)
トップスタークラスがすると混乱が予想される。
出口に並んで帰路につく観客を出迎えてくれる。立ち止まって話しかけようものなら、後がつかえるのでお客さんは外に出ざるをえない。面会は、観客が全部外に出て、ジェンヌさんが楽屋に戻ってからかける。大休憩の時間を少し長めに取る。
回収が難しそう。
チケットを切ったときにアンケートを渡して、扉に立っているお姉さんが、入るときに鉛筆を渡してくれる。鉛筆は持ち帰っても良い。観客は幕が下りた後アンケートに記入をし、帰るときに出口にある回収箱の中に入れる。回収が終わったら、まとめて演出家に渡す。
作品発表会案 しかし、スケルジュール調整が難しい。
非公式の行事として、まだデビューしていない演出家候補たちが、年に1回・10日ほどの期間で、バウホールにおいて作品発表会を行なう。劇団は必ず基本線を提示し、年毎にテーマを決める。そして、演出家候補たちは、それに沿ったものを作る。
うーん、難しいなあ。最初のはともかく、アンケートは実施して欲しい。商業演劇だから、興行的に成功すればよいのだろうけど、観に来る人はみんな違うでしょ。劇団ホームページを劇団関係者全員が見るわけではないし、偉くなればなるほど一部のファンの声しか耳に届かないようになっているようだから、こういうのを実施してくれると、嬉しい。
一番実現可能なのが、三番目だと思う。大劇場作家を育てるには、こうした発表の場を作っていかないといけないんぢゃないのか。それにバウホールって、元々、若手の修練の場とか大劇場ではできない実験的なものをするために、できたものではなかったっけ。(1997)
「密やかな要望」で示したとおり、まだ大劇場デビューしていない演出家たちが、年に1回作品発表会を行なう。あくまでこれは、私の要望である。
期間は10日間程度。
年毎にテーマを決め、劇団は必ず基本線を提示する。演出家候補たちは、それに沿ったものを作る。芝居の形式は問わない。一作品につき一演出家。作品の長さは1時間30分くらいで、ひとり一公演。
演出家ごとに各組から出演者を募り、オーディションで選ぶ。応募資格は研7以下とし、調整がつけば組は超越しても良いことにする。
主旨は、大劇場演出家の育成。ひとり3年くらい作品をだし、これを今後の進退を決める手がかりのひとつにする。つまり芝居向きかショー向きか、宝塚向きかそうでないか、という具合にである。アンケートを実施して、演出家及び劇団はそれを今後に活用する。
宝塚ファン以外の観客を求める。友の会による前売りは行なわず、大々的な告知もしない。歌劇・グラフの隅のほう、演劇系の雑誌や、市や阪急の広報誌に小さく載せるくらいに留める。貸し切り公演もなし。
チケットはどの公演も一律で、一枚2500〜4000円くらいに設定し、それとは別にパスポート券を発行する。パスポート券を買いなおかつ全作品観た人には、最終日のエスプリホールでのレセプションに参加してもらい、直接意見交換ができるようにする。
市報かなにかで審査員を募集する。審査して最優秀作品を決め、次の年ドラマシティで上演する。
例)
| 日にち | 0/0(日) | 0/0(火) | 0/0(木) | 0/0(土) | 0/0(日) |
| 開演時間 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | 14:00 | 14:00 |
| 演出 | 小柳N | 齋藤Y | 大野T | 藤井D | 児玉A |
チケット:3000円 パスポート券:12000円
パスポート券をお持ちの方は、レセプション (最終日 17:30) に参加できます。
ファントムは紫苑ゆうで、クリスティーヌが白城あやか。後の配役は考えなかったのだけど、実は、一度グラフでふたりの扮装写真を見て、「シメさん、綺麗」と思ったから。後ろで蝋燭が何本も立ってたのが妖しくて、好きでした。
要は、「宝塚版・オペラ座の怪人」をすればよいわけだ。ロイドウェーバーや劇団四季や、ケン・ヒルのだけが「オペラ座の怪人」ではない。もっとも原作者から、上演権を購入するわけだけど。「エリザベート」くらいしっかりしたものを作れば、いけると思うんだけどな。真琴つばさのファントム、結構いいぢゃん。
最近、十手ものをやっていない。十手ものは好きなので、是非。半七捕物帳でも宝引きの辰でも、実はなんでもイイ。
あのメイクは宝塚では難しいと思う。鬼、ドラキュラ、堕天使、狼男、死神ができるのだから、フランケンシュタインもでき…ればいいな。
ショーのモティーフで多い、人間(男)とアンドロイド(女)の恋の話だから、それを芝居でしたっていいと思う。(1997)
追記(2004.4.3)
* 2004年宙組で「Phantom」上演。
エスプリメンバーによるアルタ前広場のトークショーに行って来た。土曜日の一番日差しが強い時間である。なんで外でやるんだろうと思っていたら、大阪でオリンピックをやるためのキャンペーンみたいだ。大阪府も目のつけどころが違うね。でも私は横浜の方が近くていいなあ。2008年まで私が生きていればの話だけど。
実は、宝塚の人が出るトークショーに行くのは今回が2回目で、しかも最初から最後までいたのははじめてである。1回目はというと、昔コニカプラザで稔幸がやったもので、時間ぎりぎりに会場に行ったら人がいっぱいいて、全然見えなくて10分くらいで出てきてしまったのだ。だから、今回はそんなことがないように30分前には広場に行ったのだけど、結局ロープの一番前ぢゃなくて、フジテレビのカメラのそばにいた。因みに、テレビ東京のカメラも来ていた。星奈優里と目が合うなんてことはないけれど、まあ、いいや。
今回は、「大阪オリンピック開催を希望します」みたいなのだったけれど、ちょくちょく、路上でのトークショーをしてもらいたいと思う。屋内だと会場に入りにくいとかあるけど、その点屋外(特に路上)だと、フラッと寄れる。しかもただ。宝塚を観ない人だって、人だかりがあればそう無関心で通り過ぎないし。今回だって、「ナニ?」「タカラヅカ?」と言って足を止めていたコギャル風がいた(しばらくいて去って行った)。タカラヅカの広報活動としては、良いと思うんだけどな。
次回、もしまたこういった路上トークショーがあるなら、無理矢理話題をオリンピックに持ってかない、フリートークがよいのである。(1997)
漫画は読んでいないし、これからも読む気はないだろう。『虹ナタ』は、あらかじめマンガを読んでいないと、話はぽんぽん飛ぶわ、気がつくと新しい登場人物がでてきてわからなくなるわ、といったような話は聞いていたのだけど。まあ、もう植田紳爾氏だし、「理事長就任記念作品」だから、諦めませう。
だけどねえ、酷いよこれは。高嶺ふぶきのトップお披露目作品なのに、三条はやることないし、見せ場らしい見せ場もない。その上ナターシャだって突然失踪するし、「アレ、本編終わりなの?」って感じの尻切れトンボだし。適材適所ともいえない。でも、ひとつの話の流れとしてみればつまらないが、シーンごとにぶつギレで観れば、それなりに楽しいことは確かだ。
花總まりのナターシャはよかった。あの美貌と、その口から飛び出す言葉使いとのミスマッチさが観ていておもしろい。「メシだ〜」といって喜ぶところが犬みたいでかわいい。いい感じでのびのびしているし、観ていて結構気分がいいぞ。上海での
ナタ:「オレが下品で(正確なセリフはわからないけど、こんな感じ)」
三条:「うん……あ、いや(と、しどろもどろ)」
ナタ:「今、うんって言っただろ」
というやりとりが個人的には一番好きです。ハイ。
呉松梅子は、星奈優里の柄ではなかったのだ。どうみたって三条とは(元)婚約者ってだけで恋愛関係には見えなかいしさ。しかし、女のカンで、三条が蘭子に好意、しかも自分に向けられてはいなかった恋愛感情というやつを持っていることに気がつくんですね。でも「クヤシーッ!! キーッ!!」っていうのは、なんだかノリきれてなかった。最後の高笑いも、ちょっと笑いが尻窄み。呉松家が成金ということもあるのだけど、全然貴族のお嬢様っぽくない。よくある意地悪なお金持ちのお嬢様止まりなのが、観ていて欲求不満。
翠華果の竹子はかなりいい人だ。呉松家の中で唯一ナターシャに好意的に接している。武志にも親切だ。見かけそのままのおっとりした雰囲気が、竹子に合っていた。しかし、呉松家は名前にセンスがないね。新人公演の曽根綾子は怪演で素晴らしかったと伝え聞いているが、どんなんだったのだろう。観たかったなあ。竹子とは180度人格が違うから、曽根さんは。
曽根綾子は、さすがの小乙女幸なのだが、三浦環の再来なの? ちょっと遣りすぎだろう。三浦環の再来にしては。しかしあのパワーには舞台監督役(?)の風早優も敵わなかったようだ。息があがってたぞ。
なんだか結構偏った見方をしてる。男役より楽しみどころは娘役にあったかな。最近植田芝居はストーリーを追ってちゃダメだということに気がついた。でも『ベルばら』よろしく漫画をスライドで映すのだけは、やめておくれ。有効利用できてないっていうか…… (1997)
「虹ナタ」のお口直しにと思ったけれど、これも、う〜ん。ロマンチック・レビュー10作目だかなんだか知らないけれど、う〜ん。所々に、「これって観たことある」というシーンが挿入されていて、寄せ集めみたいな感じがしたことは確かだ。「虹ナタ」みたいなものでも新作をやる植紳に比べると、まとめに入っている感じする。
「イエスタデイ・ワンス・モア」で高嶺ふぶきがシンディ(花總まり)の結婚式に遭遇するところが、「夢・フラグランス」のと似ている。轟悠の声の感じが重たくて、曲とあっていないような気がした。「ヒート・ウェーブ」は、これは好き。星奈優里の悲鳴再び。「ミラクル・ファイブ」は、「ちょっと、またかいな」と思ってしまった。岡田さんはいつも男役に脚出しさせる(でなかったら、女役)。ちょっと違和感。高嶺ふぶきと轟悠のふたりで、少しおかしなことしているけど、ああいうお遊びは、一路真輝も含めた3人だからおもしろかったのではない?ちょっとつらい。「ボレロ」はかっこいい。
私にしてみれば、「虹ナタ」もあわせてさんざんだったわけで、非常につまらなかった。花總まりの出番少ないし。そのかわり若い人がいっぱいでていたので、おもしろかった。(1997)
今まで宝塚でこれは観たことがない、というものを挙げていったら、ホラー、というか、怖い話を観たことがないことに気がついた。怖いって云っても、大階段から転がり落ちそうで怖い、とか、ゾフィーが怖い、とかではなくて、幽霊とか理解しえないほうの怖いだ。轟悠バウ初主演の「恋人たちの神話」(1992年5/30〜6/9)は、バウ・マジカル・ミステリーでこわくなかったんだな。観てないけどさ。恐怖を感じる作品ではなく、むしろ笑いを取ったということが、当時の「絵と文」「楽屋日記」から窺える。
夏と云うことで、やはりあの世のもの系、この世の謎系の話がみたい。版権上無理だけど、X-FILEとか。でもよく考えたら、ショーでは多い。「ジュビレーション!」の南極の雪女とか、「ミリオン・ドリームス」のミリオンビーツとか。見終わったあとに、なんか怖いかも、と思う。まあ、南極の雪女はけっこう幻想的で、怖い感じはあまりなかった。
現実に即しているから怖いんだと云う話もあるけれど、今後あり得ないことはない、という意味で、パラサイト・イヴみたいな、バイオテクノロジー的なもの。それを云ったら、SFにまで行き着くなあ。
無理かなあ。無理だろうなあ。
ちなみに、宝塚で私が怖かったのは、「結末のかなた」の、黄金仮面を被った通行人たち、だ。もしすれ違う人や電車やバスに乗り合わせている人や、私以外の皆が黄金仮面だったら?そんないいしれぬ恐怖を抱いた。(1997)