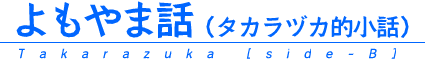
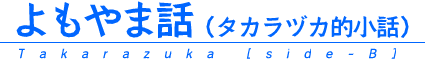
『観劇ノ記録』でもよかったが、感想とも違うので、よもやま話に。
『オペラ座の怪人』は、ガストン・ルルーによる、オペラ座の怪人は実は…という、ミステリ怪奇小説である。宝塚版『ファントム』は、オペラ座地下で育った青年と元劇場支配人との親子の物語となっている。
さて、洋の東西を問わず、一人の男がある女と恋仲になるが、諸事情により別の女性と結ばれる、という話は多い。その結果、先般の女性は、ショックからか気が狂ったり病気になったり不遇のうちに死に、男はその幽霊に悩まされるのである。
それが本当に怪異であるのか、男の良心の呵責が見せた幻かは触れない。しかし『ファントム』では、その「女の幽霊」にあたる部分が、怪人の「仮面の下に隠された顔」に相当するのかもしれない、と思う。現実的解釈をして、それがヴェラドーバが茎ごと食べた毒草の毒の作用だとしても。(2004-08-15)
2005年上半期の公演ラインアップが発表された。年々発表時期が早くなっているのでは? と云う気もしないでもない。(上半期だけなら妥当だよ)(基本的に制作準備は一年前から)
2005年明けて最初の公演。
『ホテル─』のほうは、「様々な過去、想いを抱えた人々が交錯するホテルという空間を舞台に」と云うあらすじの一文に、グランドホテル? と突っ込みそうになってしまったが、そうではなく、ラブストーリーでヒューマンドラマらしい。正塚さんの得意分野だね。コミカルタッチ、とわざわざ断りがあるのは引っかかるが。セレブ御用達のホテルが舞台なら少しは煌びやかなゴージャスな雰囲気になるだろうか。ショーは、岸田辰彌が当時観たレビューを宝塚のレビューとして再構築、と云うことでよいのかな。それとも『モン・パリ』の再構築だろうか。
彩輝直退団公演。
何と云うか、「夢よもう一度」のような気がするのだ。星組時代に、彩輝直は新公でトートを演じていて、「美しい」と云う評が少なくなかったからだ。シシィは瀬奈じゅんで、言葉は悪いが、ゲテモノ公演に近い。怖いもの観たさで、観客動員は間違いないだろうし、観る前からあれこれ云うのは簡単だけど(もう云ってるけど)、あとは始まってから。としか云いようが無い。とりあえず、何で今この時期にこの出演者で『エリザベート』なのか。その真意をフロントに問い質したい。
※記者会見をニュースでだけど見たし、あさこシシィも思ったほどキワモノではなかったけど、男役が演じるのは、宝塚のシステム的にもちょっと違うよ。
初舞台生お披露目公演。
オギー、また暗そうな。モロッコ… マラケシュ… 砂漠… 『バビロン』のマレーネのあの場面みたいな感じだろうかと、漠然と思ってみる。(絶対違う)(全然違う) 『エンター・ザ・レビュー』はまずタイトルが、酒井さんと云うよりも三木さんちっく。と云うのはさておき、『モン・パリ』自体は実際には観たことがないので、21世紀版といわれても、全然ピンとこなかったり。
現場復帰した植紳の新作にご当選。
『長崎しぐれ坂』はとりあえず原作があるから、大コケすることはないだろう。(柴田さんで観たいなーと思ったのは内緒) ショーの『ソウル・オブ・シバ!!』は藤井さんなので、これで、とんとんか。(2004-09-26)
何時だったか誰かが、「文句云うのは簡単だけど褒めることは難しい」(大意)と云っていたので、日ごろ宝塚に対する(あまり正当でもない)不満や文句が多い身としては、「いやはやごもっとも」という感じである。なので、褒めてみる。
時間になれば容赦なく客電が落ちるので、遅刻者に厳しいとも云う。(でも途中入退場は容易い)
あらかじめ告知してある時間に始まらないほうがおかしいわけで。特に小劇場演劇なんかだと、何があるのか、平気で開演時間は遅れるは、その分だけ(それ以外の理由もあるが)終了も遅くなるというのは当たり前。本当は、当たり前に思ってはいけないのだけどね。開演時間が遅れるのを見越して遅く来るのではなかろうか、と思うような観客もいて、それでまた、観客が入りきってないからと遅くなる。悪循環。
NYLON100℃とか劇団☆新感線とか、今をトキメク劇団でもそれだから(知名度が上がるにつれ改善はされてる)、重大なトラブル(緞帳が開かないとか)でもない限り、宝塚の「時間通り」と云うのは、立派と思うのです。
大劇場と東京宝塚劇場限定ではあるけれど、トイレの設置場所が多いし、個室の数も多い。休憩時間もたっぷりあるので、トイレに向かう人の波も分散され、結果えらく待たされるということがない。
青年館とか地方公演だと、男子トイレ潰しても絶対数が少ないから、あの行列を見ると、いいやもう我慢しよう、と不健康なことをつい考えてしまう。それは宝塚意外でも同じで、ある程度女性客が多いと見込んで対応できている劇場での公演を除けば、劇場が小さくなればなるほど、お手洗いとは縁遠くなる。
基本的に化粧替えがあるから、出演者側の事情で設定された長さのような気はするけれど、御手洗に行ってもお釣りが来る、たっぷりの30分である。
たとえば、今年(2004年)話題作『髑髏城の七人』では、アカもアオも休憩時間が20分。一幕終了で急げば、いくらか余裕はあるけれど、一息つくとトイレはもう長蛇の列。しかもなかなか進まない(10分待ちとか)。でも行っておかないと後も長い、という展開。これで休憩時間が30分であれば、トイレに並ぶ側の気持ちはずいぶん違う。
これも本公演限定。もちろん上演中はダメ。大衆芸能の名残と云えばそれまでか。でも、11時開演がある時点で、幕間がちょうどお昼時、というのがモノを云っているような。
大劇場館内にはレストランもあるし、東京だってビュッフェはあるけど、ちょっと小腹を満たしたり喉を潤すためにロビーに行かないでよい、というのはうれしい。客席内 OK だから、団体さんはお弁当を用意しているわけで。
他所の劇場(キレイどころが多い)で、休憩中にちょっと枝豆の袋を取り出しただけで、係りのお姉さんに「ここは……」と注意されている人を見かけると、つくづく宝塚は寛容だな、と思う。
えーと、某所にも同じ様なスレあるぢゃんとか云うのは、ナシの方向で。(2004-11-14)
観劇、批評系のサイトが年末によくやるベストなんとか。気の利いたコメントは、相変わらずできない。それにしても、2004年の観劇リストを見ると、評判作ばかり観ていたなあ、というのが実感。作品の傾向も偏っているような……。
※云うまでもないけれど、念のために一言添えると、あくまでも私的評価です。
右を向いても左を向いても90周年で、80周年のときより劇団がはしゃいでるような。
今年は芝居が不作で、ずば抜けて「これイイ!」というのはない。本公演はショーで持ち直しているので、それはちょっと酷いのではないかと。
壮一帆が「送られなかった手紙」で自信をつけ、「スサノオ」での月読の演技に反映されていたのが、収穫でした。
宝塚90周年ということで浮かれぽんちだった劇団は、ショーのタイトルに『タカラヅカ』と云う言葉をいちいち入れていたのが、印象的。でも楽しいショーが多かった。
実は好きな順なんぢゃないの、とか云わないように。わたしとしては、「飛翔無限」で春日野八千代先生の踊りをナマで観ることができ、感激であった。
映画と宝塚を含めて、今年観劇した中でよかったな、おもしろかったなと思えたものは、以下のとおり。(同じ土俵に入れますか) とは云っても、全部で50本しか観ていないうえにそのうちの約2/5は宝塚なのだから、たかがしれている。観ようと思って観なかったり、時既に遅かった公演も多かったので、取り溢しを減らすのが来年以降の私の課題か。
5番目までは順位はつけずに、上演順でリストアップ。
12月に入って観たものが多いのは、きっと気のせい。
「新・明暗」はダントツで、脚本良し、役者良し、芝居良し、で云うことなし。選曲も優れておりセットも効果的。同様に、「消失」も深く、やはり文句なし。そういう意味では、「花のいそぎ」も、出演者と上演時期、作品とがぴたりと嵌っていた。(2004-12-30)
年末恒例の総括。リピート含めた観劇回数、初見観劇回数が、過去最多となった。それでもやはり、評判作を多く観ているのは否めない。ほとんど開拓しなかった。
※云うまでもないけれど、念のために一言添えると、あくまでも私的評価(むしろ好きな順)です。
去年みたいな大きな、節目のような出来事はなかったけど、今年もいろいろあった。いよいよ来年はタカハナ体制に終止符が打たれ、一時代が終わる感。
次点で、桜乃彩音の花組娘役トップ就任。春野寿美礼ともども、攻め系の芝居になるのか。(それはどうかしら) あと、来年のベルばらでの雪組退団者が、その面子があまりにも痛すぎる。
よかったものとイマイチだったものが、二分。若手演出家の台頭が目に付く一年だった。それにしてももっと脚本、演出レベルを上げてほしい、と云うフラストレーションも溜まる一年だったかと。
『炎――』がドベなのは、キムシンの「青年の主張」は体に合わない、と云う一点に尽きると思う。
今年はわりと、どんぐりの背比べなのが多い。
フィナーレの階段降りでの手拍子が、『ネオ・ヴォヤージュ』からなくなって、今までどおりに拍手しやすくなったのは、よかった。
※雪組東京公演の『青い鳥を捜して」と『タカラヅカ・ドリームキングダム』は、リピート扱いなのでノーカウント。2004年版を参照。
映画と宝塚を含めて、今年観劇した中でよかったな、おもしろかったなと思えたものは、以下のとおり。今年も去年同様、見損ねたものが多いので、取り溢しを減らすのが継続しての課題。どちらかと云うと宝塚中心なのも、相変わらずと云うか。伝統芸能、オペラ、舞踊関係が手薄なので、そういうのも観られるようになったらいい。(映画も全然見ていない)
『うら騒ぎ』はよくできていて、たっぷり笑わせられた。『Le Petit Jardin』は当て書ではないものの(ない故?)、A班(スカイステージ放送でのテレビ観劇)B班ともに配役がぴたりと嵌っていたのと、観終わったあとの清々しさが、ここのところの宝塚では他に例を見ない。『セパレート・テーブルズ』も見応えのある上質な作品で、『Le Petit Jardin』ともども心温まる余韻が残った(空気が似てるかも)。(2005-12-31)