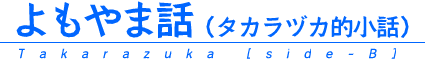
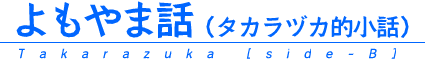
ちょっと妄想に入ってみて、具体的に誰で観たいのか、というところまで踏み込んでみようかな。
捕り物の王道、半七捕物帳。だって、最近捕り物上演してないのだもの。ここはやはり、雪組にしようかと思いきや、月組。だってマミさんの青天って好きなんだもん。でも、捕り物というと、どうしてもバウのイメージが拭えない。大劇場では、ちょっと大きいような気がするのさ。人数も含めて。
半七(神田三河町に住む岡っ引き):真琴つばさ
お粂(半七の妹):夏河ゆら
松吉(半七の子分):真山葉瑠
庄太(半七の子分):大和悠河
演出:木村信司
主要人物は、ざっとこんなものでしょう。小説は短編なので、いくつかの話を合わせるとか、半七自身の色っぽい話はないから、これは作るしかない。NHK みたいに、お粂を半七の義妹にして、秘かに想いを寄せさても良いかな。どっちにしろ、半七の相手役をどうするかだ。風花舞は、事件関係者の重要な役所。半七といいムードになる。ん。事件を起こすのは、汐風幸かな。
半七捕物帳は、確かに銭形平次とか、後々の捕り物小説に影響は与えたけれど、わりと人情話っぽくて勧善懲悪の匂いはないから、いいんでない?(1997)
(これは、1997年11月に、地元のデパートで催された宝塚写真展の感想である)
富士吉田市の人は富士山に登らない、とはよく云ったもので、それをそのまま実行しそうになってしまった。ま、ヒマな時に寄ればいいか、なんて思っていたら、もう写真展は終わりぢゃあないですか。ということで、かけ込み状態で、見てきたのだけど、2階は通り過ぎるだけ。8階は結局行かず仕舞い。ひとりでいても怪しまれない、連絡通路だけとなってしまった。
写真展はいくらでもあるけれど、ポスターは、特に昔のは池田文庫とかに行かないと無理だから、こんなに近くで見れたのはよかった。お化粧品とか、電気洗濯機の広告がばーんと載っているのが、凄い。今ぢゃあ、VISAとかが控えめにあるだけ。でも何か、いまのポスターはあまりセンスがないって云うか、ちょっとつまらないかな、という気がしたのさ。まあ、私のレトロ趣味って云ってしまえば終わりなのだが・・・
割と最近のポスターはともかく、戦前とか、結構昔のポスターは本当に見たことがないから、それはとても新鮮だった。モン・パリあたりまでのポスターだと、広告も含めて全体に統一感がある、ような気がする。EXPO '70 のものは、控えめに下の方に洗濯機の広告が載っているのだけど、ちょうどそこが一番目について、全然控えめになっていなかった。
タカラヅカのチラシって、よくわからないけれど、東宝劇場に早く行くとカウンターにのっているあれか?。劇場に行って隣の人がそれを持っているのを見るのだけど、何となくポスターをそのまま流用している感じ。お金がかかるのは承知だけど、ポスターとチラシはデザインからして全く別のものを用意してほしいなーと思ってしまう。間違いがあったら指摘して下さい。(1997-11)
(12/9/1997 13:45開演 ビデオシアター)
あんな所にあんなスタジオがあるなんて知らなかった。トイレの先って云うのが素敵。天井がむき出しなのが親近感を抱いた。
はっきり言って、見せ物としてはイマイチである。編集の仕方がひどい。私も人のことはいえないけれど、素人編集かい、あれは。スクロールとカットインだけって言うのもシンプルでまあいいけど。でも、映像が切り替わるところはぶつっと唐突に行かないで、なんか、心構えをさせてよ。それに、タイトルの「輝く銀河の中に」って何か関係あるの?
劇団が収録した映像を観れたのは貴重だったし、「サタデイナイト・ロマンス」と「FILM MAKING」と「ある日夢のとばりの中で」と「グッバイ・メリーゴーランド」が少し観れたからよかったんだけど、でも劇団収録ビデオを流しちゃうか。あれはいわば身内が見るもので、人に見せるものぢゃないでしょう。いくら好きな役だからって言っても、ねえ。ファンも身内って言っちゃったらお終いだけどさ。まずカメラが動きについて行ってない。ズームイン・ズームアップが素人っぽい。パンするとぶれてる。ビデオ化されたものはその点は安心だけどね。でも400円も払ったのがちょっと悔しいなあ。麻路さんと星奈さんのお話はおもしろかった。(1997-12)
地獄島 -お役者捕物帖-(栗本薫 1988年11月10日刊 新潮文庫)
「歌劇」1997年11月号の、宝塚絵双紙で取り上げられていて、おもしろそうだったので買って読んだら、これがおもしろい。あらすじは歌劇を見てね、って感じなのだけど、嵐夢之丞:稔幸、切支丹お蝶:星奈優里、という配役でそのまま読んでくと、なんか、いい。本当は、NHKあたりでやってくれないかな。宝塚だと凄くお金がかかるのだ。それに、一本立てにしても時間が足りない。そうそう、雪之丞の時の着物の使い回しはやめてね。ノルさんとホシナさんの濡れ場がみたいな〜、ホシナさんのお蝶はかっこいいぞ(わーい掏摸だスリだ)、って理由だけで、宝塚上演を望んぢゃうんだもんね。最後は、「つづく」っていうのがちょっと欲しい。「雪之丞変化」みたいにしょぼしょぼにならなきゃ、ぜひ宝塚で観たいぞ、と思わせてくれる一冊である。お蝶の視点でかかれているので、星奈さん主演かしら?女同士のキスシーンはどうなるのかしら?
あらすじ(『歌劇』1997年11月号より):
謎めいた過去を持つ若き人気女形、嵐夢之丞が忽然と姿を消した……。時を同じくして江戸市中で夢之丞に似た美女が次々と惨殺されていく。夢之丞を慕う女掏摸、切支丹お蝶、碧眼の怪剣士、西東幽之介、女賊雲居のおさよ、浪人秋月主殿、夢之丞の師匠嵐駒之丞…、善悪入り乱れ、運命の怪しい糸が縺れ合い、怨霊渦巻く地獄島で、今夢之丞の恐るべき秘密が明らかになる……。
1997年12月現在の星組で、しかもバウで上演するとしたときの配役を考えてみた。
(1997-12)
フランケンシュタインを宝塚で観たいと思っていたら、ナイロン100℃に先を越されてしまった。宝塚は、本当に恐い話をやらないんだよな。というのは、半分本当で半分嘘だけど、小池さんで、フランケンシュタインの書き直しを、期待したいのだ。だってドラキュラとか狼男とか、悪魔とか死神とか(妖精とか)、いわゆる怪奇系手がけているの小池さんだけなんだもの。フランケンシュタインだって、何もボリフ・カーロフのあれでなくたって(といってもあれは強烈なのでそれしか思い浮かばない)、いいぢゃん。「蒼いくちづけ」みたいに現代に復活、でもいいぢゃん。現に、医学生・フランケンシュタインがやろうとしたこと、起こりつつあるんだし。バウだったら、毒があっても「ばうだしー」で済むでしょう。そういう問題ぢゃないか。
シメさんの後、モンスターやらせたら、絶対真琴つばさが一番、と思っているのだ。クリーチャーも、実はマミさんだったらスマートな、苦悩する(やっぱ宝塚はそこで苦悩しなきゃ)怪物になるんぢゃないかなって、思うのだ。ああ、でもフランケンシュタイン君でもいけそうだ(とすると、エリザベートにはやっぱり風花か。個人的には、風花は怪物と絡んだほうがいいよなあ。なにげに「ローン・ウルフ」を引きずっているなあ)。
怪奇ついでにいってしまうと、怪談話が観たい。聊斎志異とかの中国の話か、日本の説話がいい。結構宝塚向きの話ってあると思うんだけどなあ。幽霊ものでも(それでもって恐いの)。雪組か星組あたりが、似合っちゃうんぢゃないか、って気がするんですけど、こっちは。(1997-12)
いや、とうとう値上げしましたね。買うまで実感わかなかったけれど、買ってから実感しました。1000円出しても、もうおつりが500円ぢゃないんだなあ、って。だから、柳花堂のおじさんに1100円渡した。
本当に、値上げした意味あるんだろうか。まさか阪急電鉄の赤字の尻拭いぢゃ……。あり得るなあ、なにしろ阪急電鉄株式会社・創遊営業部・宝塚歌劇団、だもんなあ。それに、大きさも、何版っていうの?中途半端でさ、置く場所に苦労するのよ。しかも、中身もつまらないし。もっともお正月号が一番つまらない、と思っているのだけど。2月号以下に期待。おまけのシールだって、トップさんだけなんだな。別に星奈さんのそれを期待していたわけぢゃないけどさ、おまけつけて値上げするんだったら、おまけなんていらないから500円のままでいて欲しかった。けっこう私の周りぢゃ、そういう意見が多かったんだけどな〜。私の周囲だけかな〜。
1997年までとどこが変わったの?っていうと、たいしてどこも変わってない。グラフ・トーク・スペシャルがなくなった(いや、まだなだけかも)。さいとうちほの漫画連載が始まった。「トウランドット」はぜひ再演して欲しいけど、連載ってことは、「来月も買ってね〜」というメッセージが暗に込められていて、私はいやぢゃ。だって露骨なんだもん。たぶん、この連載のために、私は買い続ける。そうそう、登場人物の扮装、肝心のトウランドットは、星奈優里かなって思っている。求婚する男を、謎が解けないってだけで殺しちゃう残酷な美しいお姫様は、彼女が一番似合うからだ。星奈さん以外だったらグンちゃんかしらん。でも、世の中の倫理観なんて知らないという雰囲気を、誰よりも星奈さんに時々感じぢゃうんです。私は。(1997-12)
1997年のトピックス・ランキング。1・宙組誕生 2・東宝取り壊し 3・五組目誕生に伴う組替え 4・久世星佳・高嶺ふぶきの退団 5・インターネットいろいろ
宙組が、1998年1月1日に誕生する。ネーミングの最終決定は理事長だそうで、そのことに対してちょっと不満の声も挙がっていた。一番人気の「虹組」は敢えてはずした感じである。本当に「宙組」で応募してきた人がいるのだろうか。いたとしたら、宝塚とか阪急とか理事長とかにすごく近しい人なんぢゃないかな、と邪推してみたりして。宙と書いて「ソラ」と読ませる、宝塚初のルビ付き組名になりそうな予感(っていうか、なるんだけど)。組長は大峰麻友、副組長は出雲綾、トップ男役は姿月あさと、トップ娘役は花總まり。
老朽化のため、東京宝塚劇場が取り壊されることとなった。最後を飾るのはジャニーズで、そういう決断をしたといわれる理事長に対しファンは怒り、緞帳落書き(案)に対しても怒る。あの狭いところにどうやって工事車輛が入るのか、見物である。
五組制は、世紀末なんだなあ、と馬鹿なことを考える契機となった。なんだかすごいビッグイベントに参加しているような気持ちにさせてくれたので多謝多謝。それに伴う組替えは、結果として星奈が星組に戻ってトップ娘役となったが、月影はなんだったんだ? まさか五組制を予測しないでコンビを組ませたんぢゃ……
久世と高嶺の退団は早すぎで、辞めさせられた説が結構でていた。事の真相は分からないが、その可能性は大きいぞ。特に、高嶺に対する植田理事長のコメントはそうとしか受け取れない(と高嶺ファンの弁)。さて、真実や如何に?
インターネットがますます盛んで、劇団のホームページでは、バッシングの嵐。特定のスターに向けられたものや、ファンクラブ、特定の人物、など、いろいろね。特定のスターというのは去年もあったけれど、今年もすごかった。それは悪口って言うんだよって云うような、かなり非生産的なものもあった。
今年一年、宝塚もめまぐるしい動きだった。なんだか振り回されてばかりいたようだ。(1997-12)
いやいや、花組の真矢みきが退団発表しましたね。とうとう。実は、星組に「植田紳爾」の字が踊っていたから、「まさか……」と思っていたのだけど。宙組の「エリザベート」も気になりますねえ。な〜んかいや〜な予感。どうか、はずれますように。東京公演も「一日二回公演休演日一日」という状態を脱出しそうで、いくらかスケジュールが楽になるはず。役員とかは今まで通り満員御礼でいられるかを心配しているようだけど、個人的には少し空席があったほうが、気が楽。ふらっと行って観られるようになれば、良いな〜。
今年一番気になるのは、雪組。大幅入れ替えで、昔の面影はほとんど留めてない。スター級男役は、香寿たつきを筆頭として、汐風幸・安蘭けい・汐見真帆・貴城けいと芝居ができる人が続いているし、娘役は、月影瞳が踏ん張って、「こんなぐんちゃん知らない」って思えば上出来ぢゃん。「エリザベート」新公も「ガラ・エリ」も観てないから、わかんないけど。加えて、新春公演「春櫻賦」が谷正純氏が演出の割りにはたったの二人しか死なないって云うし(でも死ぬ)、昔やってた民謡ものみたいだっていう話を聞いたぞ。帝劇は行けたら行きたい。そして、公演でとても気になるのは酒井澄夫氏の「浅茅ガ宿」(「浅茅が宿」の方がいいなあ)。やっと宝塚で「ホラー」が観れるのね。といっても宝塚だからただのホラーにはならないとは思うけど。「吉備津の釜」を石田昌也氏、「蛇性の淫」を太田哲則氏で上演したら、私は泣いて喜ぶでしょう。
星組は、とうとう植田紳爾理事長先生の番がとうとう廻ってきちゃったって感じ。「皇帝」かあ。ナポレオンかな。まりこさんがベートーヴェンでピアノを弾くってのもあり得る。しかも、これって可能盛大だ、と勝手に思っている。でも意表をついて「始皇帝」とか「カラカラ帝」だったりして。どっちみち、星奈さんにつく役には、な〜んの期待も抱かないもんね。ショーも暗そう。ヘミングウェイをショーでやるんですか?草野さん。何となく一番気が重いのが、星組である。(1998-01)
追記:
星組の「皇帝」は、ネロかあ。ネロねえ。新しい精神性の軌跡といわれても、史実に沿った内容っぽそうだし、新聞を発行していたとか、実は恐妻家でピタゴラスが良人だとか、そのあたりを扱うのだろうか。ペテロとパウロの殉教話ではなさそうだ。話の中身にはあまり期待はしないけど、どうなるのかは注目したい。「ヘミングウェイ・レビュー」も、彼の好んだ土地を題材とするんだったら、なにもヘミングウェイの名前を付けなくてもいいんぢゃ…… 生誕100周年を記念したいのなら「誰がために鐘は鳴る」を再演するとか、普通はそういう風に考えるけど、お金なさそうだしなあ。よくわかんないよ。
アーサーとリアの関係を追っていると気がつかないけれど、「失われた楽園」は結構細部が謎だったりする。たとえば「もののけ姫」で、サンはどうして山犬に育てられたのか、というのに近い疑問だったりするのだが、それを考えていくと、どうにも止まらない。
さて、エリオット・ウォーカーの妻・エルザは、名前のみの登場である。台本を見てみると、スイスの病院で死んだと云うことになっている。死因は、書いていない。では、なぜ病院にいたのだろう。読み進んでいくと、エリオットの小説「青春の凱歌」を読んで精神を乱した、とある。小説のヒロインはエルザがモデルになっているのだ。更に読み進んでいくとエルザの代名詞が「モダン・ガールNo.1」ということも書いてあった。
台本にある事実を時系列に整理していくと、
以上のことから次のようなことが推察できた。
すべての鍵は、「青春の凱歌」にある。しかし、どんな話(ジャズエイジの話らしいことは、アーサーの台詞から伺える)なのかは、一切明らかにされていない。仕方がないので、エルザがこの本を読んだことによって精神を乱した理由を考えてみた。
結論:
エルザは、一部分で有名だったにせよ、そのことによって神経症を患っていた。軽いノイローゼである。エリオットとの結婚生活によってそれが重くなったか、彼が彼女の話を聞くことによって軽減されたかはわからない。しかし、彼女をモデルにした「青春の凱歌」が、ある種エルザの症例記録のようなものであったため、それを読みショックをうけた。「精神を乱した」という言葉から心的打撃が大きかったことがわかる。かなり大きかったのか、神経症が精神病に移行した。入院後、エリオットが誰だかわからなくなったと云うのは、器質性の痴呆のせいだろう。直接的死因は不明。おそらく、衰弱死。
結構強引なのだが、衰弱死としたのは、普通の病気(この当時だと結核)になると、身体全部で生命を守らなくてはならなくなるからだ。あくまで素人解釈なので間違いだらけだと思うが、以上が「エルザはなぜ死んだか」という答えである。小池さん、何で彼女は死んだんですか?(1997-08)
追記(2004-04-24)
エリオットはアーサー・フィッツフェラルド、エルザはフィッツフェラルドの妻ゼルダがモデルと考えられる。彼女は精神を病み、療養先の病院で火事により焼死した。
宝塚は自称他称とも「夢を売る」ということになっているので、「夢」のない舞台は大部分のファンにとっては有り難くない。この「夢」というのはどういうものか、という考証はおいておくが、「人ヲ殺ス」というのはおそらく「夢」の部分と対局にあるのではないかな、と思う。
その場合、不可抗力やそうせざるを得ない、という点での殺人は、受け入れられる。殺したことへの苦悩や、殺そうと決めるまでの経過が細やかに書かれていることが多いからだ。例を挙げると「二人だけの戦場」で上官を撃ち殺してしまったシンクレアや、「夜明けの天使たち」青年館バージョンでのアルヴァ、キレちゃったジョシュアである。ここで、どうして殺しちゃったのだろう、と考えることは不毛だ。
それとは反対に総スカンを食らう殺しの場面というのがある。それは谷正純氏の描くものに多い。最近では「EL DORADO」だろうか。とにかく谷さんは死体累々なのである。虐殺の場面を描くのにも、たとえば、虐殺をする側のある一兵士が、個人的には反対だけど組織の中では個人が抹殺されて実行せざるをえない、その辺の苦悩を書くための描写とかだったらまだわかる。けれどそうではなくて、虐殺される人たちは主人公と共に行動していることが多く、主人公と対立している人物(顔の見えない個人ではないのがポイント)が乗り込んできて、容赦なく殺してしまう。「主人公とその仲間たちは死んでしまいました。かわいそうですね」というノリなのだ。
殺し場で書いたように、私には理想の殺し場像があるので、それを考えてみる。そうすると、やはり前者になる。無差別殺人ということにしてみたって、そうである。無差別にしても理由はあるはずだ。動機不明の殺人も同じ。殺すことが最終目的かもしれなくても、そこに至るまでを追っていけば、後者でなくなるはずだ。(1998-08)