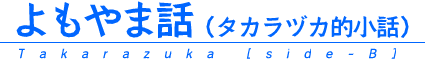
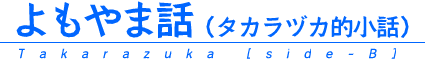
前に、「花總まりのモノクロポートがちょっとだけアンニュイな天下の月山紀子っぽい」などと書いたが、よく考えたら、全然似てないことに気がついたので、取り消す。月山紀子とは、フジテレビで放映されていたドラマ『きらきらひかる』に登場する、松雪泰子が演じた熱血刑事だ。
さて、ショーで見てみたいカンジのもののことを書く。
それは、「へヴィメタ・ジャズ」である。宝塚のショーの音楽に関しては、いろんな要求(ロックはもうちょっとちゃんとやってほしいな、とか、クラシック調なのにべたべたエレキベースの音が邪魔してないか? など)があるが、一方で宝塚で歌謡曲やってもな、という思いもある。宝塚にしてみれば、観客の年齢層が広いくてターゲットを絞れないから、音・リズムともになるべく激しくないのにする必要あるだろう。しかしここは敢えて、「へヴィメタ・ジャズ」を使ったショーを、私は見たい。
理由その1:どうせ「へヴィメタル・ロック」をやっても、そうは聴こえないだろう。
理由その2:ロックとか今時の音楽よりスタンダード・ジャズのほうが得意そうだから。ただし、FREE STYLE以降のジャズはロック同様苦手だろう。ステファン・グラッペリはできる。
理由その3:「プログレ」ができるんだから、やれば出来るんぢゃない? 「エリザベート」もいわゆる宝塚っぽい音ではなかったし。
理由その5:コムロ音楽をはじめとするの耳障りのよいサウンドしか知らない人に、ショックを与える。また、ジャズに興味を持ってもらうきっかけにする。
理由その6:個人的シュミ(←これがかなりのウェイトを占めている)
場面設定は考えてないけど、中詰めのパレードってのはどうかしらん。ムリだって?
そういう見方でいくと、テクノもいいな。テクノっていったって昔のテクノで、クラフトワークとかYMOみたいのなら、少し歳がいった人でもわかるでしょう。芝居で(なくてもいいけど)映画の『メトロポリス』っぽいのをやれば全然違和感ないんだから。 (1998)
ときどき、宝塚がする表現で、絶句してしまうものがある。芝居で超現代物をやるとそれが多いキライがある。絶句、といったって某U氏の「宝塚って、すごぉ~いわぁ!!!」ってな具合のセリフに呆れて声も出ないのではなくて、「これはちょっと違うでしょう」という表現上のものだ。
いま、一番「オイオイ」と感じているのが、『国境のない地図』である。1995年の作品である。ベルリン封鎖から壁崩壊までをヘルマン・マイヤーというピアニストを通して描いている。で、そこで登場する西独パンクロッカーっていうのが、「それって」というシロモノなのだ。ただのロック野郎ぢゃないんだよ。パンクだよ、パ・ン・ク。なのに、なぜそうなるんだ?!
なんだかメタルっぽくなかったかなあ。外見が。髪の毛逆立てたパンクロッカーてもいいのだけど(←そうか?)、あまり形式張らないのがパンクだと思ってんで、ちょっと違和感感じちゃったのさ。皮着てるし、メイクも濃い。それに、音楽もちょっとね。聴いていて、椅子からこけそうになってしまいましたわ。もっとも「パンクの青年」っていうだけで「パンクロックをやってる人」というわけではないのだけど(たぶん)、それにしたって、なんか納得行かないのだ。あれヘンだよ。
ここからちょっと音楽的なこと。個人的には、パンクというとロンドンパンク、「The Clash」や「Sex Pistols」などのバンドをイメージしている。『国境のない地図』と時代的にはちょうど良いパンクバンドではないかな。イギリスだけど。日本のパンクだと、「THE BLUEHEARTS」かな。これもけっこうステロタイプだ。でもまあ、そんなわけで、パンクに限らず宝塚はロック全体に対する認識が甘い、と断言してしまうよ。 自信を持って大丈夫なのは、ロカビリーとロックンロールくらいだと、これも断言できる。
芝居でロッカーを登場させるなら、その周辺の事情(ジャンルと衣装の関係、時代性との関係、音的なこと など)を、特に演出家はある程度把握しておいてほしいな。 (1998)
本編は好きではない。外伝と番外編は、ル・ルーもでてくるし(というよりか、ル・ルーが主人公みたいなもんだ)、こっちのほうが内容も私的にはおもしろい。アンドレも眼悪くなってないしさ。登場人物はうんと減って、フェルゼンもデュローデルもアランもいないけど、出そうと思えば出せるし、娯楽大作にしようと思えばできるんだよ。外伝は比較的捕り物っぽく(そうでないのもある)、番外編はベルサイユを離れてどこか田舎で、青髭公爵の女版で、ちょっとだけサスペンス(?)仕立て。演出は巨匠ではなくて小池さんってのはどうかな?
佐々木倫子のマンガ。宝塚向きではないと思ったんだけどね、バウ・コンでやったらおもしろいかな、って思って(ここでふと頭に描いたバウ・コンは、サミーさんとリンゴさんとミユさんの三人でやったもの)。ほかに、『代名詞の迷宮』とか『動物のお医者さん』なんてのも考えたんだけど、スパイだったらいくらか演出的に派手にすることもできるだろう、という意図もある。でもなあ、ハムテルがスパイになったようなモノなんだしな~。『動物のお医者さん』だったら、ファミリーランドの動物使えるけど 『代名詞の迷宮』に収録されている「代名詞の迷宮」も、とぼけたやくざのお嬢様の恋が絡んだ話だし、いいかなあ ここは気軽に中村暁氏とか、谷正純氏におまかせしたい。彼らに、佐々木倫子の作品に流れている、ある一定のノリ(ぢゃないな 感覚?)が消化できるか疑問だ。
完全に個人のシュミに走った。だいたい宝塚でやるなんて、天変地異が起きたって絶対ムリ。でも久世星佳も映画版に出演していることだし、記念しましょうよ。秋の『踊る大捜査線SP』もあることだし。なにも湾岸署でなくていいんだから。宝塚歌劇前署(宝塚署は実際ある)とか、いっそのこと設定だけパクッて、どこか海外の話にするなんて、どう? 「な~んにもお手本にしていません」とか云って。テレビのは、あらかじめ犯人は視聴者に提示されているけど、宝塚でやるときは謎解きも有りでさ、それに『コメディーお江戸でござる』(NHK総合)の笑いと、『女ねずみ小僧』(1989年 フジテレビ)のノリと、ちょっとだけほろっと来る部分も入れて、「涙あり、笑いありの100分」 なんて。正塚先生にお願いしたいが、「如月恵」みたいな人は出さないでね。石田先生ってのもなかなかいいかもしれない。しかし本署と所轄の関係って、阪急と宝塚に置き換えられそう
萩尾望都は、やっぱやらんとね。『トーマの心臓』はもちろん観たいけど、『ポーの一族』も好きだよ。私観てないんでわからないのだけど、紫苑ゆうの代表作『蒼いくちづけ』は、いくらかこれを参考にしているのかな? 萩尾望都だったら、やはり小池さんでしょう。でも萩田さんというのもいいな。こうなったら宝塚版の『半身』も観たいのである。(1998)
知っている人は知っているけれど、私は「殺人犯役」が好きである。演出家の谷正純氏が、「死ぬときにはその人の生き様がでるから芝居で人を殺すんや~」という旨を、星奈優里にインタビューされて語っていたが、それに近いノリで、私は人殺しの役が好き。でも、人を殺すという行為に感情がべったり入り込んでいるのは嫌だ、という捻くれ者である。
殺人犯にも好きなタイプというのがある。最近は、できれば男性より女性がいいなあ、と思うようになった。和歌山保険金詐欺事件の件でテレビ局からコメントを求められたどこかの弁護士が、女性と男性との犯罪の違いを語っていて、「そんなものかな~」と思ったから。今となっては何を言っていたのかよく思い出せないのだけど、犯罪まで「女性らしい」「男性らしい」なんてばかみたいぢゃん。宝塚は、女性が男性を演じていて、さらにその男役の相手としての女役がいて、セクシュアリティが歪んでる(悪い意味ではないよ)。だから、女役がいわゆる「男性らしい犯罪」をしてもいいんぢゃないのか、と思った。女役が男役より強くなってもきているしね。
閑話休題。
殺人の手段は、しつこいようだが、1)ナイフ 2)ピストル 3)その他 の順番になる。断然ナイフがいい。ピストルの場合は、持った姿が絶対サマになるだろう、という理由で一部生徒(例えば星奈優里とか)に当てはまる。そうね、所要時間はあまりかからないほうがいいかな。あっさりと、ドライに。
殺人の種類は、無差別猟奇殺人。無差別にしたって理由はあるので、そこを、主人公(ということはトップ男役さん)は深く探っていってほしい。目的としての人殺しでも、手段としての人殺しでも、どっちでもいいけれど、怨恨だとか、痴情のもつれだとか、それだけは、それだけは絶対にやめて 感情が入り込むのがイヤなのは、『やさしさの精神病理』(大平健 1995年 岩波新書)を読むと、なんとなくわかります。
犯人は、「正常な」大人ではない。子供とか思春期の若者の犯行でもなく、でも、あまり年とっているのもなんかなあ。20~30代くらいの、若い人がいいなあ。ほかの人と一見なんら変わらないのだけど、よくよく考えてみると、ちょっと逸脱している様子がうかがえる(でもわからない)、なんて。
この点は、どうしたって宝塚の「清く正しく美しく」の理念とは相容れない。でも一部演出家の手に掛かれば、うまく描かれることも知っている。
かなり極端な犯人タイプであるけれど、今ちょっと頭にあるのは、『踊る大捜査線秋の犯罪撲滅スペシャル』の大塚寧々と、『踊る大捜査線 THE MOVIE』の小泉今日子である。雰囲気的にこの二人は、なかなかいい感じ。
余談:このとき大塚は、男の暴力に耐えかねた末の犯行(殺人未遂)だったけれど、犯行内容はともかく、彼女はなんだか『サイコメトラーEIJI』以降なんだかココロここにあらずという感じが強くなってしまった。 (1998)
仮劇場である1000days劇場から、東京公演も阪急管轄になった。劇場は、有楽町にある、東京都丸の内庁舎跡地を借用して建てられているので、借地代がむちゃくちゃかかる。当然、それは、座席料金値上げに跳ね返ってきた。現行の値段は、安くして精一杯の金額だ、という話をどこかで聞いたことがある。が、本当にそうか?と思って、複雑な事情を無視して、単純計算をしてみた。
| 料金 | 合計 | |
|---|---|---|
| A席(304席) | ¥8,000 | ¥2,432,000 |
| B席(983席) | ¥7,000 | ¥6,881,000 |
| C席(642席) | ¥5,500 | ¥3,531,000 |
| D席(60席) | ¥3,500 | ¥210,000 |
| E席(42席) | ¥2,000 | ¥84,000 |
| 合計(2031席) | ¥13,138,000 |
表1は、現行の数値である。要は、この合計金額と同じかそれ以上になればいいのだから、
| 料金 | 合計 | |
|---|---|---|
| A席(304席) | ¥10,000 | ¥3,040,000 |
| B席(983席) | ¥8,000 | ¥7,096,000 |
| C席(642席) | ¥6,500 | ¥624,000 |
| D席(60席) | ¥3,500 | ¥2,247,000 |
| E席(42席) | ¥2,000 | ¥204,000 |
| 合計(2031席) | ¥13,211,000 |
表2のように、改定してみた。座席に若干の変更を施してある。
個人的に、安い席は多いほうがよい。何度でも観れるし。宝塚の収入の多くはリピーターによってまかなわれているのではないか。そうしたときに、末席が42席、次に安いD席が60席の計102席では、どう見ても少ないと云わざるをえない。C席になると5500円となり、3回以上の観劇は(私は)ためらわれる。
D席・E席は、安いうえに少ないので、チケットが案外取りにくい。そこで、C席の値段を下げ、A席の値段を上げることにした。改定A席の10000円という値段は、今までの宝塚公演と比べたら高いが、ほかの同規模劇場で行われる芝居に比べればいくらか安い。また、A席のような前のほうの座席となると自然と座れる人も決まってくる(というとかなり語弊があるが、まあいいや)ので、問題はないだろう。
改定B席は、A席・D席・E席をこの値段に設定すると、これ以上安くできない。そのかわりC席を若干安くできた。しかし、それでは値段に開きが生じてしまうので、A席の値をさらに上げることで対処する。それでもB席は500円ほど今より高くなってしまう(表3)。
| 料金 | 合計 | |
|---|---|---|
| A席(304席) | ¥11,500 | ¥3,496,000 |
| B席(887席) | ¥7,500 | ¥6,652,500 |
| C席(96席) | ¥6,500 | ¥624,000 |
| D席(642席) | ¥3,500 | ¥2,247,000 |
| E席(102席) | ¥2,000 | ¥204,000 |
| 合計(2031席) | ¥13,223,500 |
以上、つらつらと改定金額を書いてきたが、どんなもんでしょ。でもいくら値段を安くしたって、客が入らなきゃ意味ないから、劇団は、「絶対観に行きたい」「また観に来たい」「ほかの人にも観せたい」と思えるような作品を作ってほしい。 (1998)
85周年かなんだか知らないけれど、必ず再演(芸術祭大賞受賞)作品をやるのね。80周年の時はそんなことなかったのにね。別にいつも通り普通にやればいいぢゃん、と思ってしまうのはなぜかしらん。しかも『ノバ・ボサ・ノバ』と『ザ・レビュー』は2組連続公演だ。以前『歌劇』でアンケートしたときも『ノバ・・・』は再演希望が多かったが、『ザ・レビュー』共々なにも連続でやらなくてもいいのではないか。植田紳爾の作品が2作なのもなんかねえ。でも「変更になる場合もある」って書いてあるから、わかんないぞ。『WEST SIDE STORY』は、せっかくある権利なんだから、という無理矢理感が強い。星奈優里がマリアだったら、どっちかというとイヤだなあ。
シェークスピアばっかり。まあね、ひとり一回くらいは経験しておいたほうがいいに越したことはないのだが(結構おもしろいし)、こんなだと、シェークスピア以外も観たいよねえ、と天の邪鬼になってくるのさ。でも私はシェークスピアは嫌いではないから別にいいんだけど。個人的には、『ヴェニスの商人』が観たいなあ。でも『十二夜』やるからいいや。主演・演出ともに若手が多いのは結構なことである。
「1900年代最後の年だし、ついでに85周年だし」ってことで、お祭り騒ぎなのかな。80周年の際は、月組:バトラー編/雪組:スカーレット編『風と共に去りぬ』、ロンドン公演、手塚作品、大運動会、以外は取り立てて普通だった(と思う)。どうみたって劇団だけが盛り上がっている感じで、ファンは置いてけ堀な雰囲気である。
しかし、こうやって今のところ発表されているスケジュールを見ると、どうみたって忙しすぎなんだよね。5組になってスケジュール的に楽になると思ったら、前と変わらないか、むしろ忙しいのではないのか。生徒が怪我したら、元も子もないぞ、劇団!(1998)
恐ろしいことに、雪組と星組しか観ていない。ちょっとこれはまずいよなあ。観劇本数も、宝塚以外を含めたって全然観てないし。しかも、星奈優里がトップ娘役に就任してから「星奈さんが出ている作品で東上するの(←このへんからしてやる気がない)は全部観よう」と、決めていたにもかかわらず、カネ・ヒマ・根性がなくて『イコンの誘惑』は行かなかったという 振り返ろうにも振り返れないのである。
1998年トッピクス・ランキング
不況なので、1位~3位のみ。(1998)
さすがに、ロケットは人数が少なくて空間がすかすか。はっきり云ってけっこう物足りない。それに5組になってスケジュールが楽になったと思いきや、大劇場公演と東京公演の合間、またはその逆に、やれ地方公演(全国ツアーという言い方もイマイチだなあ。ジャパンツアーで良いぢゃんか)、やれバウホールだ、日本青年館だ、と前より忙しいんじゃないのかな。1999年は博多座での公演もあるし、これ以上生徒を酷使してどうするんだ、劇団。楽しみは増えたけどね。
これで、クサさを売り物にするトップスターがいなくなってしまった。ひとつの時代が確実に幕を閉じた。
本当に突然の出来事で、エ~ッという具合だった。これからグンと伸びておもしろくなるところだったのに。劇団は結局彼女を生かし切れずに手放してしまった。さすがに男役の添え物的な扱いは減ったが(あったよね、『皇帝』とか云う作品が)、それにしても娘役に対する認識が甘いんぢゃないのか、劇団は。
大劇場でやった作品は全部東上することになるので、「東上しないから観に行ったほうがいいのかな でもめんどくさいや」ということがなくなるので、よかったよかった。仮設劇場のわりには結構しっかりしているが、客席が寒いのをなんとかしておくれ。
1.今までさんざん、『歌劇』(や『グラフ』)のカラーポートや舞台の写真が悪い、とかなんとか言ってきたのだが、編集担当者のセンスとしてはあれがベストチョイスなんだよね。それに今まで気がつかなくてゴメンナサイ。
2.『皇帝』が文化庁芸術祭のどの賞にも引っかからないのは、まあ当然でしょう。よくよく考えたら、宝塚は「舞台をみて深く考える」とか「主義主張を訴える」という性格のものではない。宝塚の最大の特徴であり強みは、「スケールが大きい」「観て楽しめる」「コスチュームプレイができるし全然違和感がない」なので、『皇帝』はツボは、まあはずしていなかったわけだ。観て楽しめはしなかったけれど。そういった意味では、娯楽作品を作り続けている植田紳爾氏に、今までさんざんわかってなくってごめんなさい。
楽しいですね~。観ていてこんなにラクなお芝居を宝塚で観るのは、久しぶりなのであります。宙組の人たちものびのび演じているし、いいカンジ。まだ緊張でがちがちな初舞台生の口上のあとだから、よけいに「肩の力抜いてやってんな~」という気がしただけかもしれないけれど、できたてほやほや、宙組お披露目の公演だというのに、この余裕はなんなのだ!? それに各組精鋭で、「手放すのが惜しい」っていう人がごそっと、宙組に行ったわけでしょう。全く持って贅沢な組なのである。
この話をおもしろくしたのは、やっぱり、あの悪役たちなのだ。スタイン騎士塾が掲げている騎士道の心得の対極に、例えばクリストファー(和央ようか)がいたりするわけでして、結構その対比もオモシロイ。いかにもっぽい造形なのがかえって幸いして、騎士団たちの言う「勇気・寛容・慈愛」云々も、すんなり伝わってくるのだ。同じファンタジー系でも、大義名分を振りかざしていた『白夜伝説』とは大違いである。
そのクリストファーである。彼の馬鹿さ加減がとても気に入っている。盾を鏡にして髪を整えているとか、どうして黒い騎士なのかその謂われや「へ~ん、し~ん」と歌うところとか、まったくバカだなあ。モーガン(夏河ゆら)の妖術でエクスカリバーを抜けるようにしてもらったって、ちっとも嬉しくないだろう、って思うのだけれども、本人は「エクスカリバーが抜けた」ということが余程うれしいみたいだし、剣を抜いた自分に陶酔しているところが、なんとも言えない。あとになって、モーガンを妻にしなければならないことに気がついて真剣に悩んでいるのも、本当に馬鹿だよねえ。ウシシと笑っちゃうんである。結構セコイし、キザで自己中で自分勝手でナルシスだし、私が彼の真後ろにいたら、はたきたくなってくるような奴だけど、こんなにヘンな人もいないのだ。和央ようか、なぜこんなにハマってるんだ。
夏河ゆらもモーガン役で、「また鞭持ってる」と思いながら観ていたのだけど、あんなにエキセントリックな役が似合う人もいない。蜘蛛の巣の衣装もすごいけど、魔法が解けた後もすごいよ。ディズニーアニメのパロディみたいだ。
あとどうでもいいんだけど、真中ひかるのスタイン卿が、なんか誰かに似ていると思ったら、大学で地域メディアを教えているY教授だった。髭の具合のせいかもしれないけど、彼に似ているのか。う~ん。
しかし、不満だって全くないわけではないのだ。まずはNHK! タイトルロールの入れ方がよくない。プロローグは2カメの引きで撮しているんだから、上側が空いているんだからそこに流してくれなきゃ、もろに出演者に被っちゃってる。
吟遊詩人(湖月わたる)の語るエクスカリバーの話を役者が演じている、という構造で、観客を二重の観客に仕立てたのがおもしろかった。この吟遊詩人は、なんでもナレーションしていくので、芝居の流れが分断されてしまうので困った。
あと、ケイトは、少なくとも陵あきのがやる役ではない(そしたら彼女はなんの役をやるのだ、という話になるが)。人材豊富な結果かもしれないけれど、ちょっと違うなぁ。ジェイムズに対して兄以上の感情があるのかはっきりしないし(「血が繋がってないもん」と云っているからあるのでしょう)。ポール(朝海ひかる)に対してお姉さん的な存在のは、彼がちょっと気の毒なくらいよくわかった。いっそジェイムズと同年かちょっと年上にして、ほんとうは好きなんだけど、サクソン人というだけで最初は嫌いだったロザラインも、実は結構いい人だしハッパをかけちゃう(そしてあとで後悔する)、っていうのとかでも良いよね。終わったことだけどさ。
でも、なにはともあれ、お披露目公演らしくて、明るく楽しく、満足です。(1999)
ショーは、基本的に「○○さん、カッコイイ」とか「衣装がきれい」とかっていう見方をしている。で、ショーはそういう見方でもいいと思っているのだけど、そういう意味では、『シトラスの風』は、いい線いっていたのである。「明日へのエナジー」のずんこさんは特にかっこよかった。ショー自体のおもしろさ、とはまたちょっと違うけれど。
場面的に見れば、「ノスタルジア」は、1860年シチリアっていうナレーションがまったくワケわかんないし、あれはあってもなくても関係なさそうだ。ストーリー仕立てのわりには、ストーリーが???である。座談会をあとで読み直して、なんとなくわかったけど、最初は、観ながら『夢・フラグランス』(1992年/月組/岡田敬二)の紫陽花の場面の焼き直しを想像していた。でも、雰囲気はいい。
「誕生」も、仮面のところはやけにリクツっぽい。もっと楽しくやろーよーと私は思ってしまった。そのあとのバードとつながりがあるのかないのか、さっぱりわからん。バードのところは「誕生」っていう章のタイトルが合うけど、絶対前半の仮面の場面は蛇足のような気がする。別にしたほうがよかったね。
「花占い」はけっこう好きである。しかし、私は、花總まりがどうしても最後が「キライ」になっちゃって花びらをぶちぶち引きちぎるもんだから、花の精が怒って逆襲にでている場面だと思っていた。
ショーを観た印象は、姿月あさとと花總まりのコンビは爽やか路線だ、ということだ。路線といったらヘンだけど、たとえば、真矢みきや麻路さきみたいに「こってり絡んでくれないと落ち着かない~」というその逆ということだ。こってりという文字が不似合い。(1999)
宝塚の代表作は?と訊かれたら、『ベルサイユのばら』と答えるだろうなあ。けれど、私はベルサイユのばらはあんまり好きではない。平成ベルばらがきっかけで宝塚を見るようになったのは確かだけど、あくまできっかけにすぎない。だからもし、ウエシンが突然「新東京宝塚大劇場のこけら落としは、ベルばらです」なんて言い出そうものなら、即座に反対したい。しかし、ウエシンが「ベルばらの外伝をやります。演出は小池修一郎クン(個人的希望 植田景子さんや児玉明子さんでもいいな)です」といったなら、諸手をあげて賛成しよう。
マンガでも、本編よりかは、外伝のほうが好きである。特に集英社からでている、「ベルサイユのばら10巻 黒衣の伯爵夫人」が好きだ。それは、エルゼベート・バートリ(いわゆる、女青髭という人ですね)をモデルにしているとか、個人の嗜好の問題(だって、殺し役だよ)とか、そういったことが理由である。
ベルばらの本編を上演するなら、外伝だって宝塚で観たいよ。ただ、この10巻は無理っぽいのだ。『歌劇』(1998年11月号)で中島梓氏が「『地獄島』は宝塚での上演は無理」という根拠と、だいたい同じなのである。なぜって、まずゲスト主人公のモンテクレール伯爵夫人は、美しさと若さを保つために近隣農家の若い娘を誘拐してきて残酷に殺し、その血に浸っている、ということになっているからだ。マンガの中に一カ所でてくる殺人シーンも、殺し方としたら、宝塚的にはえぐいほうかな。
その次に問題なのは、伯爵夫人とロザリーとのキスシーンがあるんだな。すみれコードが邪魔をするんである。男女の絡みだったら、『ダル・レークの恋』みたいな宝塚的にはR指定だよねぇってのもアリだし、男性同性愛者も登場するようになってきているけど、少なくとも私は、お芝居に関しては娘役同士のそういった絡みって知らない。ショーなら、新しいところでは『ヘミングウェイ・レヴュー』の「ヘミングウェイ・カクテル(第二次世界大戦)」で、にゃんちゃんとそんちゃんが妖しく踊ってたけど、芝居とは違うし。
そして、決定的なのが、登場人物が少ないこと・・・・・・。
でも妄想するんだもんね。1999年1月6日現在の現役星組生徒によるスペシャル配役だ。っていうか、シュミまるだし。
| 登場人物 | 説明 | 配役 |
|---|---|---|
| オスカル | 近衛隊長で男装の麗人 | 彩輝 直 |
| アンドレ | オスカルの影 | 音羽 椋 |
| ロザリー | 諸事情でオスカルと同居している娘 | 妃里 梨江 |
| ル・ルー | オスカルの姪、ちょっと不思議な女の子 | 美椰エリカ |
| モンテクレール伯爵夫人 | モンテクレール城の、美しい女主人 | 星奈 優里 |
| カロリーヌ | ロザリーを苛める娘 | 亜づさ真鈴 |
| テオ | 伯爵夫人の筆頭召使い | 秋園 美緒 |
| ジョベール | 行方不明の時計技師 | 英真なおき |
| リオネル | モンテクレール城にいる美青年 | 朝澄 けい |
| オルタンス | オスカルの姉、ル・ルーの母 | 彰乃 早紀 |
どんなもんかな。モンテクレール伯爵夫人を星奈優里に振ってしまったので(アハハ)、若手中心&だいぶ無謀な配役になってしまった。フランスの田舎の話にしないで、ベルサイユ近郊とかパリなんかが舞台だともっと登場人物を増やせるし、そのほうが華やか。そしてリオネルを、モンテクレール伯爵夫人の虜になった青年にして、彼女のために若い娘を誘拐・殺害しているという設定にしてしまえばいいと思う。大劇場で上演するには話が小ぶりなんだけど、バウでやるには大きい。(1999)