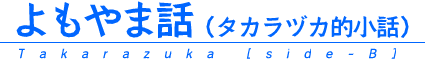
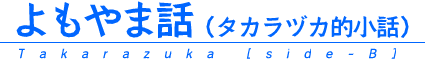
なにも宝塚だけに限ったことではないのだが、どうも宝塚では、日本物はあまり人気がないらしい。昨年の雪組東京公演も、空席があったしなあ。制作費は・・・結構かかるかも。プロデューサーが「リピーターが見込めないから駄目」と云ったとかで、植田理事長を嘆かせている。内部の人間が言っちゃおしまいだよ、というところまではいいとして、客が来ないなら来させるのが内部の人間の仕事だろうと云う植田氏には、ぜひとも客が呼べるような日本物を書いてください、とワタシは言いたい。人に押しつけちゃダメだって。
さて、日本物にどうして人が来ないのか。どうしてでしょう。理由がわかれば、きっと劇団だって苦労はしないよね。なぜなのかって理由を素人なりに考えてみた。
以上は、私が植田和物ショーをみたときに感じることである。場面展開が1部22〜25場と速い酒井澄夫氏についても、ほぼ同様の感想を抱いてしまう。では、お芝居のほうはどうかというと、
宝塚とは関係ないけど、テレビの時代劇で勧善懲悪の決まり切ったパターンが(たとえば8時45分に印籠がでるのが)いやだって言う人もいたなあ。
思ったんだけど、作り手も見る側も、和物というとどこか構えてしまうんぢゃないんだろうか。確かに所作とか面倒なことも多い。でもそれは洋物でも同じだろう。また、歌舞伎とか浄瑠璃とかで「芸術」とか「伝統」とか云われちゃって、なにか高尚な物のような気がするのもいけない。本当は、キッチュなままやればよいのに、どこか「ゲージュツ性」みたいなモノを重んじちゃったりするわけ。お客さんは、宝塚で芸術品を観ようとなんて思っていないんだから(って私だけかな)、芸術祭かなにかでたまたま賞をもらえれば、「あげるって言ってくれるんだから、ありがたく頂戴します」くらいな気持ちで良いと思うのだ。これは日本物に限らないけど。
あとは、上演にあたってのターゲットを絞りきれてない。老若男女のどの人たちが観てもおもしろい物が作れれば一番良いんだけど、「時代劇は老人の見るもの」という観念が一般にもあるのに、宝塚を観る人に同様の観念がないとは言えない。宝塚の場合はもっと深刻かな。「日本物はつまらない」だから。だったら、いちばん見せたい層をどこかで決めちゃって、それを中心に企画を立てていったほうが懸命ではないだろうか。
で、いま宝塚でやる日本物の形はどういうものがいいでしょう。私は「時代劇」だと思う。けどテレビの時代劇をそのままやったらつまらないから少し絞ってみると、
自分が観たいものなんぢゃないの、といわれたら、そうなんである。しかし、最近の日本物見渡してご覧なさいな。上記したものに当てはまる演目はない。「『浅茅が宿』は怪談でしょ」というあなた、あれはあくまでも「舞踏詩」。怪談面は二の次だったんです。したがって、あんまり怖くなかった。だけど、今流行っているものを見回すと、日経新聞の文化欄ではないけど、ミステリーでしょう。宝塚も流行に乗って良いと思うのだ。加えて、捕り物ならそれなりのスピード感もでるし、立ち回りの場面も作れる。完全な勧善懲悪にはしないで、悪いほうからもスポットを当ててみるとか工夫をすれば、「ワンパターンぢゃん」という批判をかわせる。
江戸時代にこだわらなくていいなら、王朝物とかって云うのもいいな。あの時代はやたらと物の怪が横行しているし、見た目が綺麗だし。警察権を持つ検非違使という役職があるではないか。
ということで、忙しいかもしれないけど、ベテラン作家が監修というかアドバイザーにたって、若手演出家に任せてみる、という風にすれば、若い人なりの既製のものにとらわれない新解釈で日本物もできるし、宝塚でも日本物が廃れないし、一石二鳥。ここで大事なのは、ベテランの意図している日本物と方向が違っても頭ごなしに方向転換させないことである。間違ってるならば指摘すればいいのだし、それ以外だったら好きにさせればいいのだ。(注:1999年バウは、シェークスピア三昧だが、ベテラン演出家が、監修にあたっている作品もある)(1999)
困ったときのヒマネタ 第?弾 「最近の宝塚な出来事」(1999-04)
4/15 O.A. の「Rainbow Cafe」が録画できていなかった。新聞を読まないで行った私も悪いんだけど、前回、前々回と、23:00からのリピートを録画していたので、それではいけないと思って、気合いを入れて「朝9:00」に、録画予約をしていったら、MXTVの、フィラーのようなヘッドラインニュースが延々と入っていた。思いこみってコワイ。しかし、この日の夜は、TXで手塚治虫をやっていて、スタッフロールが見たかった私は、ちゃんと予約をしたのに、あとで見返したら、これがなぜだかドラマの途中。実は先週4/8日の大鳥れいの回、これもどういうわけか頭が2分くらい切れちゃっている。人的失敗なのか、どこか機械がおかしいのか、原因不明のままだが、「夏の番組改編時に、また宝塚特集やんないかな〜」と思っている。それにしても、大鳥れいっておもしろい人だ。けっこう好きになってしまった。ぜひ、愛華・大鳥コンビで、ハッピーエンドで明るい話(喜劇なら尚よし)を見たいぞ。
2月〜3月にかけてなので、随分古い話だけれど、珍しく宝塚の夢をたて続けに見たのだ。2月は「大和路月間」だったので、梅川の夢だ。あんなコトやこんなコトしている梅川だぞ。梅川って酒癖悪いよ。 そして、3月は、星奈優里の登場。珍しく星奈さんがでていて内容も悪くない。いつもおなじ時間に乗り合わせているかなにかしてて、向こうがこっちのことを知っていてくれていた、というそれだけなんだけど、無性に嬉しかったのだった。しかし、もっとほかにも見ていたような気はするんだけど、覚えてないな〜。
「WSS」は相変わらず食わず嫌いで、星奈優里が出演するにもかかわらず、チケットを取らなかった。発売日に外出の予定が入っていたという条件を差し引いても、気が乗らなかったのだ。なにがいけないんだろう。土日はチケット売り切れているし、ひょっとしたら見に行けないんぢゃないだろうか…… いいのか?今年はちょっとはまじめになろうと思っていたのに。
そんな考えているひまがあるのなら録画した香港公演を見ればいいのだけれど、まだひとつ気が乗らないので、花組チケット売れ残りの理由を考える。結構これは花組&花組ファンに失礼な言い方かもしれないけれど、ごめんなさい。
最大の原因は、やっぱり真矢みきの退団ってことはあるだろう。でも過去の人(この言い方も失礼だけど、ごめんなさい)にいつまでも縛られていたって発展はないのだから、ぢゃあどうすればいいのかな。
多分、個々の生徒のファンによる動員は、もう見込めないと思うのだ。ファンクラブが暗躍してあちこちに手を回しても、たとえば会員に観劇のノルマ制を布(強)いたとしても、無理でしょう。となると「内容の充実」ってことしかないではないか。
「内容の充実」といっても、これは「話題性」ではない。そういう意味でいうと、『夜明けの序曲』って内容に魅力を感じなかったのだ。ワタシは。いくら「芸術祭受賞作品」であっても、つまらないものはつまらない。半分くらいは「植田紳爾が書いたものだし」という偏見もあることは認めるけどさ。愛華みれ&大鳥れいのお披露目で、タイトル的には「夜明けの序曲」で合っていて、新しい演劇形態を作り上げた川上音二郎の話なので、もとは退団公演用に書かれた芝居だとしても、素材としては新生というカンジ。でもね〜。
さて、ここで、数ヶ月前に観た大劇場の記憶と、元旦生中継の印象だけで、『夜明けの序曲』考を展開するのはフェアーではないと思ったので、千穐楽以外はチケットが残っているらしいから、一度1000days劇場公演を観て、『夜明けの序曲』を考えることにする。以下次回に続く(はず)。(1999-4)
と、云うわけで、観に行ったけど……本当に、気の毒なくらいお客さんが入っていなかった。C席。観劇2日前にチケット買って、C席前から2列目(24列目)なんですよ。これは、尋常でない。
内容だけで判断すると、『夜明けの序曲』は、お客さん来ないのもうなずけるんだな。NHK BS-2で元旦生中継をやったけれど、あれを一回観れば、「ま、いっか」って感じだもんね。チケット売れ残りは、ここにあるとみた。「舞台はナマものだから劇場に来ないと」云々とはよく言われることだけど、今回の場合、劇場に来る理由としたら、1.愛華みれと大鳥れいのお披露目だから 2.自分の好きな生徒さんを観たい 3.一回は劇場で観ないと気が済まない 4.テレビではフィナーレを観られなかったから の、どれかになること間違いなし。
ただやっぱり「芸術祭受賞」しているだけはあって、きっと昭和57年の時点ではそれなりのニーズに合った作品だったのでしょう。なんかあの頃って、日本人以外による日本文化論とか日本批判が流行ってたんだそうだ。だから音さんが「日本人」とか「日本の美しい秩序」とかにこだわってみたり、モルガンお雪さんが舞っちゃってお茶点てちゃったりするし(これは松本悠里だからって気もする)、「外国人はあんなこと言ってるけど、実はそうぢゃないんだよ〜ん」という、植田日本論の展開だったのだ。と、言うのは強引な解釈かな?
今回の再演にあたって、それは本当に観客の観たかったものなのだろうか。日本演劇界を新しく切り開いていった川上音二郎にこれがお披露目の愛華みれ、という着眼点は結構いい。それに大鳥れいと女優第一号川上貞、というのも合っている。問題は、「もう一回みたい内容」ではないこと。テレビで満足しちゃうような内容であること。
それはどういうことかというと、『夜明けの序曲』の場合、スケールが大きい話に見えて実はそうでなかった、ということなのだ。あのオッペケペーの川上音二郎である。オッペケペーの話でもよかった(むしろそのほうが、音二郎の破天荒ぶりが伺えて、愛華のためにもよかったのでは?そのかわり貞の出番がない)。『夜明けの序曲』のストーリーを活かすなら、日本に収まりきらなくて海外進出し慣れない外国で「日本」に対する思いを強くしてもいい。
だからといって、結局日本人同士のべったりした義理人情の話を絡ませるのは、どうかとおもうのだ。三味線やお茶を出せば本当に日本っぽいことなのか? せっかく外国に行ったのに日本回帰しちゃってるし、世界が小さい。話が内向してしまっているのである。自分は結局東の小さな島国の人間なんだということに気づいて、ではどうしたのか? なんだか『夜明けの序曲』はすごすごと日本に帰ってきたというイメージのほうが強いんだよね。外国に行ってなにを学んだのか、とかっていうよりも。もっとも帰国後すぐが病床に伏せる音二郎なので、功績は総て台詞で説明、というのも・・・
また、最終的にはここにたどり着いてしまうのだが、「合うか合わないか」「好きか嫌いか」という次元になるんぢゃないかな。植田氏の作品は、植田歌舞伎っていわれるように様式美だとか、パターン化された動作が多い。台詞を含めた総てが大仰というか、それを受け入れられるかどうか、ということなのだ。
加えて今回の演出陣が、それぞれの色をつけられなかったことも大きい。台詞を言う人が正面向いているし、その他大勢は「そうだそうだ」と声をそろえているし。「静かな演劇」を宝塚でやることもないけど、演出家が違うんだから、そこら辺を変えてもよかったのでは、と思うのだ。もっとも監修に植田紳爾があたっているので(そりゃそうだ)、思い切り変更できなかったこともあるだろう。だったらなんで彼自ら演出しないんだってことになるし、だから演出は酒井澄夫・三木章雄両氏によるもののはずであるのに、「植田もの」と言われ敬遠されるのである。
もともと、植田氏の指向は「大量生産」だし、もともと近場の客にアピールする舞台づくりなのだから、テレビで見れば、バーチャルA(S)席体験できるし、いっかい目にすれば(それ以上に台本読めば)ストーリーもわかるし、そこら辺が、劇場に足を運ばない理由なんぢゃないかな。
ということで、誰が何と言おうと植田紳爾の作品だったため、ということをとってつけたように結論として提示して、『夜明けの序曲』を考えてみた。以上。(1999-05)
『螺旋のオルフェ』は、今から楽しみだ。タイトルからしてホラ「螺旋」だから。スパイラル。ねぇ。こうなると、寺田っちの音楽は合わないでしょう。硬質なイメージっていうそれだけでツボにはまっているので、あとは実際この目で観るだけなんだな。ちょっとだけスパイ物で、マミさんもちょっとだけ裏世界の人だし、檀ちゃんもイワクツキナ女だしね。曰く付き、大好きっ! しかし荻田くん、ロン毛をやめて金髪にしたら、絶対にケラリーノ・サンドロヴィッチに似ていると思う。宝塚のケラさんだ。
『タンゴ・アルゼンチーノ』は、ちょうど夏休みの頃(予定)やっているので、向こうまで行こうかなと考えている。それにしても大鳥れい、人妻ですか。タモさんはビセントに次いで人妻と恋に落ちるわけだ。爽やか南国人の愛華と、こってり大阪人大鳥(←東京来たら蕎麦を食べなさい)のコンビなんで、さっぱり〜中庸〜濃厚と様々なラヴシーン対応だから、それだけでなにかあるはず。大筋だけ読むと艶っぽい話になりそうだが、小池さんはたまに期待させて落とすからな〜。ちょこっとだけ期待してみよう。
恐怖の植田っち第2弾『我が愛は愛の彼方に』。星奈さんのチョゴリ姿がとにかく美しいのは、『アナジ』の尹玉琴で証明済。ってなに着ても綺麗だけど。またしてもふたりの男性に愛されて大いに悩む役所(想像)だが、植田物にしては破綻がないってハナシだし(それは原作があって植田氏のオリジナルではないから)、これは植田物の割りにはちょっと期待してもいい・・・かな・・・ それにしても万姫ってこれは何て読むのでしょう?まさか、まんま「マンヒメ」ってことはないだろう。わかんないけど。「ヨロズヒメ」かな?(これだとむちゃくちゃ日本語読みだ)
新人大野拓史くんの『エピファニー』も別の意味で、注目したい。彩輝さんがでるってこともあるけど(いつから彩輝ファンになったのでしょう さあ)、日本物でしょう!? でも、見た目からいくとはまるな、これは。で、エピファニーって、イエスが生まれたときに東から来た三博士をお祝いするキリスト教の休日(1月6日)のことらしい。でも顕現日っていうと神が現れた日のことで、ひらめきのことでもあるから、十二夜なんだけどパパラギチックな話になるのでは、と秘かに思っている。 (1999-07)
『宝塚GRAPH』1999年7月号のアンケートは、もうそんな季節なのかと思わせたが、グラフ向上のためにもちろん回答をする。どのくらいアンケートの結果が反映されるのか、今までの実施例では掴みにくいが、望むならば、アンケート集計結果なども事後報告として載せてほしい。
8月号の"わらしべ"は星奈さんだ。だが、ミーミルが"わらしべ"に指名されたとき「出た!!」とか書いていたくせに、星奈さんだと「ふ〜ん」なのが、編集子某の好みを如実に物語っている。少なくとも私は、あの「ふ〜ん」っていうどうでもよさそうな感じが不(愉)快だ。あれ、星奈ファンをかなり敵に廻したんぢゃないかと思うよ。
中国公演は、意外でした。次に海外公演するならば、日本文化解禁になった韓国が真っ先に選ばれるだろう思っていたからさ。ホラ、宝塚ってそういうの好きぢゃん。しかしね、香港公演とたいしてタイトル(→内容)が変わんないというのが、嘗めてるよね。『ブラボー!タカラヅカ』だ? ここで宝塚讃えちゃって良いのか? 北京と上海に相応しい作品とかいってさ、「レッド・ランタン」とか平気であげちゃいそう。おまけに「月組選抜」だしね。地方公演ぢゃないんだからさ、宝塚選抜でなくて良いのか? ローテーションの都合もあるだろうけど、海外公演くらいはいくら招聘といえども「宝塚選抜」で「これがタカラヅカだ!」って魅せるのが、スジではないか。「まさかアジアだから宝塚選抜にするまでもないと思っているのでは?」って穿った見方もできちゃうよ。香港もなんだかんだいって宙組「プレビュー」公演だったし。おまけにまたしても植田&三木で、一抹どころか多大な不安なのである。特に植田紳爾氏はなんとかしてほしい。彼奴の日本物は宝塚はおろか日本文化すら誤って伝えかねない。
『夜明けの天使たち』日本青年館編と、バウホール編のビデオがやっと発売される。嘆願運動が実った結果だし、前例を作ったことで、今後もこういった活動をすれば劇団が動いてくれることが証明された。って、ワタシなんにもしなかったんだけどね。
今日を含めて、3日連続で宝塚の夢を見た。珍しいこともあるものだ。第一の夢にして星奈優里。目の前で星奈さんが歌ってんのに、必死で手紙書いてんだな。しかもJR王子駅のホームで。第二の夢は、檀ちゃんと夏河さんと、あともうひとりだれだか忘れちゃったけどやっぱり娘役さんが踊っているというものだが、ひょっとして『螺旋のオルフェ』の資料映像を見たからか? 第三の夢には、花總まりが出た。たばこのようになにかの薬物の臭いが体に移っただけで、なんか警察にチェックされてたんですよ。で、同じくミーミルも足止めくらっていたんだけど、そばにいた人(友人B)が点呼取るときに「花總さん」って、言わなきゃいいのに言っちゃったっていうところしか覚えてないんだけど、そういう夢だった。すごいな。3日連チャンで娘役トップが登場しているぞ。あとは大鳥さんとぐんちゃんだけだな。
『MAC POWER』1998年5月号のバーナード・クリッシャーのコラムの形式を真似してみました。 (1999-06)
6月某日、朝日ニュースターで次回花組公演の制作発表をやっていたのだが、音声オフにしていたがゆえに、ストーリーやら出演者のコメントやらは全くわからなかった。『歌劇』や『グラフ』のあらすじだけを読むと、なんか期待しても良さそうかなあという様子がうかがえるので、ここは未見『タンゴ・アルゼンチーノ』、ということで、まだ観ぬどころか舞台にすら上がっていない作品について、あれこれ想いを馳せてみようと思う。しかし、ベースとなる『黙示録の四騎士』どころか、「『黙示録』ってナニ? 四騎士ってダレ?」状態なのである。
ココ一番の見所は、やっぱりアルゼンチンのタンゴ青年フリオ・愛華みれと、美貌の人妻マルグリード・大鳥れいの、恋のアラベスクだろう。「タンゴが巻き起こす恋のアラベスク」って、文字だけ見ればなんだかちょっと楽しげなのだが、一体なんなんだ? でも、手っ取り早く云っちゃえば、不倫だよね〜。加えて「愛の葛藤のドラマ」である。悩んぢゃうんである。
「愛華みれと不倫」といえば、『哀しみのコルドバ』で、タモさんビセントはレイチェルさっちゃん扮する人妻メリッサと、駈け落ちしていた。ふたりはラブラブで、ビセントはメリッサの旦那を決闘で傷つけてしまうのだ〜。不倫という時点で、日本青*年純潔運動***本部が聞いたら、宝塚に韓国製グレープ味あめ玉(あまりおいしくない)を送ってくるかもしれないが、わたしはフリオとマルグリードには、期待しちゃうね。ステロタイプな宝塚のことだから、タンゴでアルゼンチンと掛けたなら、それは情熱なので、舞台が PARIS だろうとなんだろうと、濃厚なラブシーンがあるのでしょう。いや、きっとあるに違いない。
さて、解説しかわかっていない状態で出演者のことに触れるのは、あまりにもキケン過ぎるので、これは次の機会にする。音楽は全編タンゴで彩られるのだろう。タンゴなので、ピアソラが聴けるぞ、たぶん。これはイイ。
ということで、「続・未見『タンゴ・アルゼンチーノ』」は、『グラフ』『歌劇』1999年8月号を購入したあとに、つづくっ!(予定) (1999-07)
という25$のゲームが、Macにはある(クォーターノート・ソフトウェアのサイトからダウンロードできるはず)。RPG なのだが、全部英語なのでかなりめんどくさい。しかし、音楽が非常に宝塚調なのである(音楽はQTmidiファイルなので、窓ユーザーでもQTがインストールしてあれば聴けるはず)。で、「Endless Love」が思った以上に尾を引いている私は、次はペルシア物でもいいよね、って思ったのだ。わかりやすいでしょ。
雪組の『再会』は全然肩の凝らない面白い話だった。あんな感じの、冒険活劇風ペルシア物が見たいのである。星奈さんで手塚治虫の『虹のとりで』なんかいいナ。しかし、ここはひとつ、大鳥れい主演でいってみたい。
大鳥れい主演というのには、ワケがある。「宝塚GRAPH」1999年8月号、花組TCA'99 ルポで、「美麗組」レディース総長ということになっていた彼女だが、「あー、そんな感じする」と思い、妙に納得してしまったのだ。オトナの女性もいいかもしれないけど、ハジけてキレちゃった役も案外イケるんでない?ってわけ。
で、つぎに『再会』の公演プログラムにあった「DIAMOND」というエッセイを思い出したのだ。プログラムに公演とは関係のないエッセイを載せるよりも台本載っけてくれよ〜、っていうアレである。その中の、政府と盗賊とが知恵比べする宝石「カリナン」の話を、上手く料理して宝塚でやらないかな、と。そこで大鳥さんはね、盗賊の女首領をするんです。町の少年とか市場の女とか宮殿に仕える娘とかに変装したり、あと「敵」方の人間(宝石所有者のペルシアの若き王とか、宝石を守る軍人とか設定次第ではいくらでも)との濃いラブシーンはもちろん外せない。でまあ、丁々発止のやりとりがあって、最後は大円団っていうのは、どうでしょうかね。もちろん、人はひとりも死にません。
大鳥さんは結局盗賊稼業は続けるし、恋人はそれを取り締まる立場のまま。宝石は「螺旋のオルフェ」風にそんな物は始めから存在しなくてもいいし、ふたりの愛こそ宝石に勝るものだとかいうテーマを取って付けたように引っ提げて、「たまには明るい話を書いてね」の荻田さん、もしくは「非西洋を突き進め」児玉さんあたりで、観たいな。とにかく若手か、若手でなければアイロニーの太田さんがいいですね、演出は。なんて。
「千夜一夜物語」をひっぺ返してみてみたら、案外ありそうな話だとも思うんで(アリババ……ってのがあったな)、劇団様々、どうかひとつよろしくっ!(と、いってみたりして)(1999-08)
感想までは行かないのだが、『螺旋のオルフェ』について日々思っていること。予想以上にはまってしまったのは、『Endless Love』の比ではない。
『螺旋』の世界は、むちゃくちゃ("のれん分け"前の)ZABADAKだな。『飛行夢 sora tobu yume』(32XM-97/Alfa MOON RECORDS/1989)が一番顕著で、「飛行夢(そら とぶ ゆめ)」あたりがとくにそうだ。イヴはアデルの悪夢を終えられない。テーマは「過去に囚われて現在に立ちすくむのではなく、過去を抱いて未来への一歩を踏み出す」なのに、延々と「未来の拒絶」を描いているから、そういう印象を抱く。「飛行夢」Cメロの歌詞「声もだせず 何も聞けず ひとり 迷うだけ 砂の路を 歩きまわる 夢の中でさえ」「瞳消えた 人の中に ひとり 迷うだけ うごめくように 終わりを待つ 夢の中でさえ」なんて、イヴの冒頭のモノローグっぽいぞ。「砂煙りのまち」は、詞はともかく旋律が『螺旋』である。「人形たちの永い午睡」も、アデルを殺したあとのイヴの喪失感のような気もしないわけでもない。挙げていくとキリがない。
なぜゆえにZABADAKの連想が働いたのか。6/8拍子でぐるぐると同じところを歩いている感じとか、ギリギリな感じとかっていう共通点はあるのだが、曲の持つ無機質さが、イヴの虚ろな心っぽいのですよ。上野洋子の声はNav Katzeのそれと違い無機質ではなく、どちらかというとクリアなのだが、それがかえって、癒えることのない傷の深さのようでもあるのだ。吉良知彦も歌はあまりうまくないけど声が孤独だし、前向きとかそんな感じが一切しないところが、イヴと重なり合うのである。
(ZABADAKついでに云うと、『真夜中のゴースト』湖の木陰の場面の音楽も、別のZABADAKの音楽に似ていたりする。この場面は実際のトラッドを使っているのか参考にしたかはわからないけれど、ユーロトラッド風という点で共通点がある。)
シヴィルは、此岸と彼岸のどっちだと訊かれたら、確実に彼岸側にいる人。だからアリオン以上にイヴを俯瞰して眺めている感じがするのは気のせい? アリオンは、イヴに「生か死か」の選択権を与えるが、シヴィルは死への引導を握っている。なぜなら、イヴの見るアデルの幻は、彼女を媒体としているからである。イヴにとってシヴィルは死への誘惑。そしてシヴィルは幻のアデルである。メビウスの輪のようにまた元に戻って終わりが見えない。だからイヴはすべてを終わらせるために、世界の終わりを夢見ているのである。
きっと通常公演ならどこかで描かれたかもしれないアリオンとの出会いは、推測するしかない。アリオン以上に向こう側の匂いが漂う以上、シヴィルの存在そのものが死ではないだろうか。亡命時にいなかったことを考えると、その時はまだアリオンと知り合う前だったのか、本当は一緒に亡命してきたがたまたまその時その場にいなかっただけかのどっちかだが、いずれにせよ、一度死んだのを、アリオンによって生き返させられたのではないかと、予想する。(1999-09)
月組のパンフって、『螺旋のオルフェ』と少しのエッセイを入れ替えただけで、雪組とたいしてかわらなくって、哀しくなった。それにやっぱり脚本がないと、気が抜けててほかとかわらなくて、ダメだね。商業演劇を謳い始めたからそれは仕方ないのかな? でも、パンフレットも含めて宝塚は宝塚だとしたら、脚本が掲載されたパンフレットは、よそと差別化する意味で、効果的ではないかと。足並み揃えちゃったら絶対これから生き残れないって。なんで脚本削除しちゃったんでしょう。劇団からの説明ってなにかありましたっけ? 知的所有権の確保かな? 600円(その前は500円)で作品の脚本が読めるのは宝塚だけだったし、宝塚ってスゴイよねって思っていたのだが…… 「商業」なら、サービス内容の変更をお客さんに説明しないといけないし、できないとマズイんではないか? それも顧客サービスだと思うのだが、どうでしょう。
執筆料払うお金があるなら、脚本載っけてほしいんだけどな。今のパンフは削れるところもいっぱいあるし、値上げは紙代とカラー印刷代と、原稿料って気がする。エッセイは絶対要らないと思う。読みたいと思わないから、腹が立つ。さて、今のパンフレットで6000部売るのと、前の脚本を掲載したパンフで6000部売るのと、どっちが劇団にとってメリットあるでしょう。
さて、今のパンフレットを私なりに改訂して、脚本を掲載するとしたら・・・(例は月組東京公演「螺旋のオルフェ」「ノバ・ボサ・ノバ」)
なんとか18ページ浮きました。脚本を載せるとするとぎりぎりか足りないくらい。レイアウト次第では、もうちょっとページに余裕がでるはずだし、モノクロ出力で浮いた印刷代でページ数も増やすこともできる。
でもなんか「宝塚のすることだからしょうがないよね〜」って云う流れに乗って、パンフレットはあのままいきそうだね。劇団は、改訂したことによるお客の声も少なくてよかったよかったと、安堵するのだろう。
(と、改訂前の脚本付きのほうがいいと思っている人が大多数だという前提で話を進めてしまいました。もしかしたら、こんなこと思っている人は数少ないのかもしれない。)(1999-10)